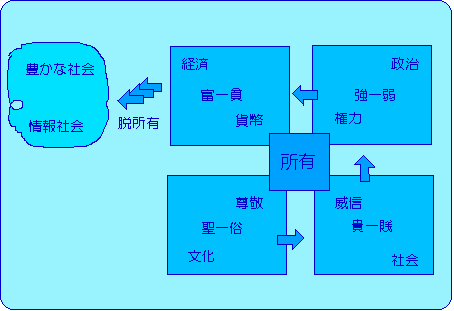|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.もっと大きな変化が? 産業社会からの変化は、それを含んだより大きな変化として認識する視点が重要である。豊かさと情報化は、所有を超えた社会構造を形成する点で、いままでの社会構造の構成方法とはまったく異なった方法論を要求する。だから、産業社会からの社会変化という常識的な見解を超えて、もっと大きな歴史的な変化でもあるだ。 大胆に主張すると、いままでの歴史は「所有」とくに「ものの所有」をめぐる社会構造の変化の歴史であった。誰がものの所有にかんして「正当化された権利」を付与されているのか、その権利の正当性の移行の歴史がいままでの人類社会の歴史である。では、その権利はいかなる変容を示したのか。 ここではつぎの4つのプロセスが考えられる。それはつぎの4つの一般的なメディアの所有をめぐる正当性の歴史である。つまりある時代にあって所有を正当化する根拠となる一般的なメディアが何であるかによって、時代は4つの所有をめぐる歴史を生成したのだ。(図3)
最初の社会段階は、「聖と俗」の社会カテゴリーから始まる。社会の秩序(社会 生成の意味づけ<世界観>)は、基本的には「聖なる人であるか」それとも「俗(非聖)なる人」かという「文化」次元でのカテゴリー軸によって構成され、そこでは希少な価値(世界観)の所有は「聖なる人」のレッテルを獲得している社会層に正当な権利が付与された。ここでは、所有の根拠は、聖なるものを生み出すパワーであり、その所有者こそ誰からも尊敬されるパワーを獲得し、俗なる人々にたいして無限のパワーを行使する正当性を獲得していた。マジカルパワーの超越的な志向は、社会のコスモロジーを教える基本であり、社会の文化価値を支える基盤である。社会秩序の基本(世界とは何か)に明快な解答を用意する呪術的・宗教的な言明は、それが奇跡として表現できるならば、そこでは無限の尊敬(その裏の畏怖)を生みだし、「聖なる人」のカテゴリーを生成する。これが社会の始まりであり、呪術的・宗教的な社会の登場である。 文化の基盤が整備されると、その社会的な形式にかんする秩序化が求められるようになる。そのとき、かつての文化次元で「俗なる人」のカテゴリーに帰属していた社会層から、ある一部が力を発揮しはじめる。それが「貴と賎」のカテゴリーを誘発する。しかもこのカテゴリー化は都市と非都市のカテゴリーに関連する。つまり「雅と鄙」のカテゴリーがそれである。都市に住む雅な貴族であることが、社会の形式的な秩序を形成する原点になる。ここから、非都市に暮らす鄙びた生活をする「賎なる人」との弁別がでてくる。都市の発見によって、「貴なる人」が社会(都市)形式のモデルとなり、社会の形式的秩序が生成される。この場合、社会の秩序を正当化するのが「社会的な威信」である。貴族の雅な生活様式が都市のあり方を決定することで、社会的な威信とは何か、が規定される。こうして、ここに新しい貴族生活が形成される。威信をもつもの(貴なる人)ともたない人(賎なる民)との弁別が社会の秩序を形成し、都市と非都市の秩序を確定する。 このような時代は、さらに、賎なる民の中から、物理的なパワーをもつものが台頭することで、新しい段階に突入する。それが「強い者」と「弱い者」の社会的カテゴリーである。ここでは政治的・軍事的なカテゴリーが社会の目標達成を決定する。社会を実質的に機能させるには、社会の秩序形式のもとで、さらに社会的な動員をかける能力の有無が不可欠になる。それが政治であり、軍事である。権力というメディアをいかに所有するか、がここでの社会問題になる。権力を獲得した強者がこの政治的な社会を所有し、その権力を所有できない弱者は服従することで生きる。歴史的には、封建社会がこの社会段階である。 しかし弱者のなかでもその一部の弱者は、その時代を新しいものに変革する力を秘めていた。それが貨幣を所有することであった。貨幣をもつ「富なる者」(資本家)と、もたない「貧しい者」(労働者)との社会カテゴリーがここに発生する。産業革命はここでの新しい社会変革のシンボルである。経済的交換のプロセスを経ながら、貧富の格差が生成され、いままでにない新しい社会が形成された。ここでは、貨幣をいかに多く所有するか、というゲームがすべてである。そのゲームの勝者が社会を制するパワーを獲得する。この新しい近代産業(資本)社会は、社会の目的達成のための便益や手段を調達する社会であり、貨幣はその調達の程度を示す一般的なメディアである。経済次元が、文化から社会そして政治へと移行してきた社会秩序の原理をここで完結させる。かくして所有をめぐるすべての流れは、一応の完結を示し、つぎの新しい段階へとステップをのぼるのである。 そのスタートが「豊かな情報社会」である。そこでは、豊かさは、その「獲得」という段階から「表現・表出」する段階に移行し、情報社会はそれに呼応して、情報の「所有」から「共有」へと移行し始める。これこそがまったく新しい「豊かな情報社会」の基本的な構成原理である。新しい社会の予感とは、この構成原理をいかに具体化するかであり、50年代の大衆消費社会とはそのための準備段階であり、過去の産業社会から離陸するための過渡的な社会にすぎない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||