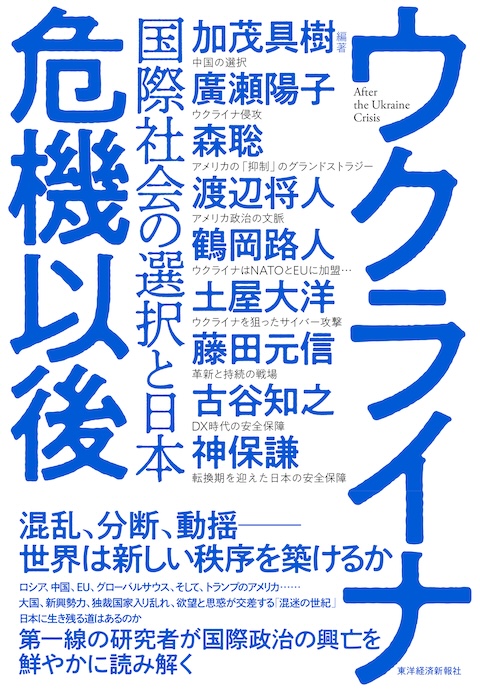
土屋大洋「ウクライナを狙ったサイバー攻撃――ハイブリッド戦と反ハイブリッド戦」加茂具樹編著『ウクライナ危機以後―国際社会の選択と日本―』東洋経済、2025年。
なかなか時間がかかった本が出ました。最初の構想段階ではウクライナ戦争さえ起きていなかったと思います。加茂さん、皆さん、お疲れさまでした。

土屋大洋のブログ
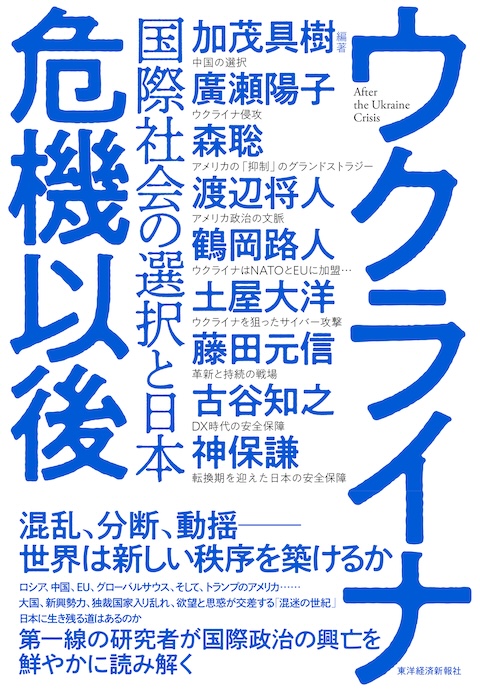
土屋大洋「ウクライナを狙ったサイバー攻撃――ハイブリッド戦と反ハイブリッド戦」加茂具樹編著『ウクライナ危機以後―国際社会の選択と日本―』東洋経済、2025年。
なかなか時間がかかった本が出ました。最初の構想段階ではウクライナ戦争さえ起きていなかったと思います。加茂さん、皆さん、お疲れさまでした。
Motohiro Tsuchiya and Kristi Govella, “Undersea cables and the extension of empire: The rise of Britain, Japan, and the United States and the competition to connect Hawai‘i,” Marine Policy, Volume 181, November 2025.
オックスフォード大学のKristi Govella先生との共著論文がMarine Policyに掲載されました。ゴヴェラ先生は今はオックスフォード大学にいらっしゃいますが、その前はハワイ大学におられました。その際、海底ケーブルのプロジェクトを実施しておられ、2023年10月のワークショップに参加させてもらいました。本論文はその成果です。
Marine Policy誌の「Undersea Cables, Geoeconomics, and Security in the Indo-Pacific: Risks and Resilience」特集ページもご参照ください。関連論文がまとまっています。
また、本論文にはNTTワールドエンジニアリングマリンの長崎の海底線史料館の資料も使わせていただきました。ありがとうございました。
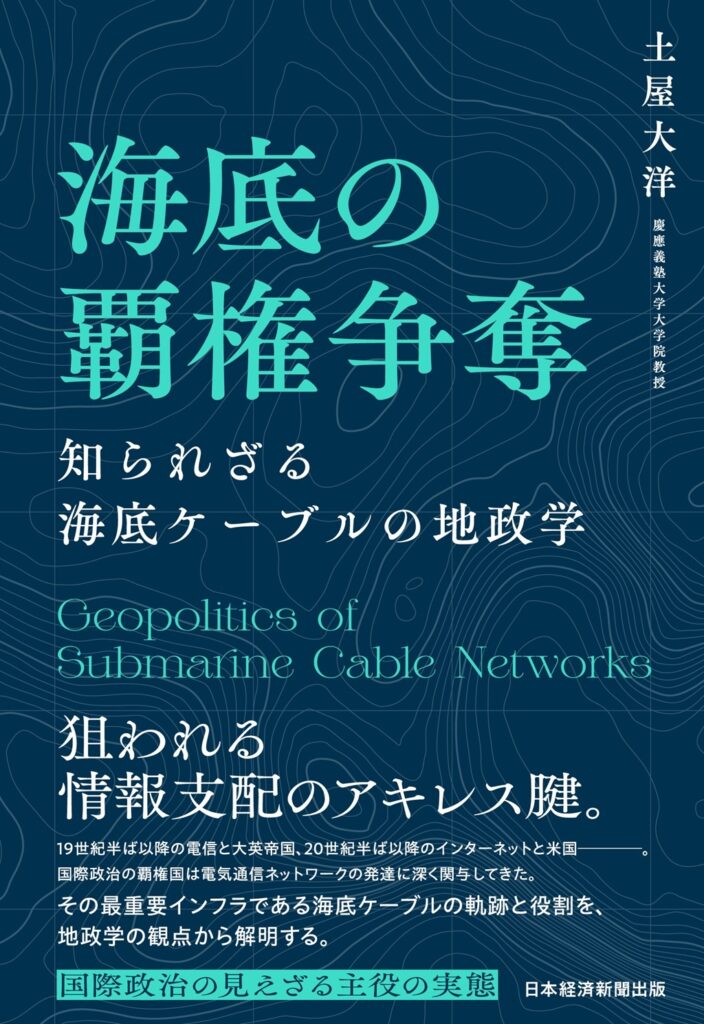
土屋大洋『海底の覇権争奪—知られざる海底ケーブルの地政学—』日本経済新聞出版、2025年。
ずいぶん時間がかかってしまいましたが、海底ケーブルの本をまとめることができました。長い間待ってくださった出版社には大変感謝しています。本当に多くの皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。
土屋大洋「ソーシャルメディアを介した外国からの選挙干渉の現状」『東亜』2025年3月号、2〜9頁。
霞山会の『東亜』編集部からのご依頼で書きました。日経の中外時評より長い文章がなかなか書けなくなっていて苦戦しました。同僚の渡辺将人さんも「米国のTikTok規制と民主主義が直面するジレンマ」と題して書いておられます。
土屋大洋「宇宙・サイバー・電磁波領域をどう防衛するか」秋山昌廣、小黒一正編『論点解説 日本の安全保障—防衛基盤の強化と防衛力の持続可能性を考える—』日本経済新聞出版、2025年、231〜247頁。
こちらは京都大学の関山健先生にお願い事をしたところ、では、こちらを書いて欲しいとご依頼をいただきました。電磁波領域はいずれ本格的に取り組みたいテーマです。
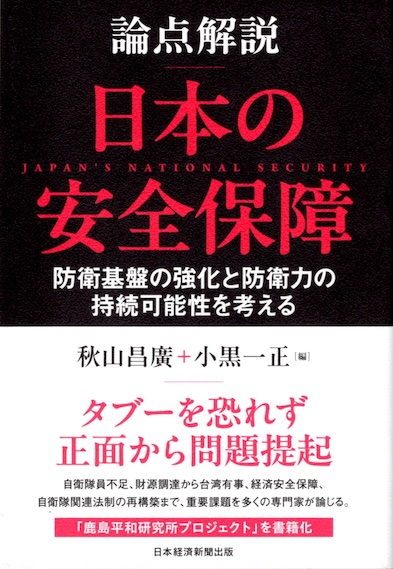
土屋大洋「サイバーセキュリティ」国際経済交流財団編『国際経済政策シリーズ5 ポストウクライナにおける国際秩序—グローバル・ミドルパワーとしての日本の役割—』国際経済交流財団、2025年、94-101頁。
非売品なので、書店では手に入らないと思います。ポスト・ウクライナにおける新しい国際秩序を考える研究会の成果です(私はほんの少しだけ参加しただけですが)。北岡伸一先生がとりまとめをされました。
2024年も終わってしまいました。前半は大いに働き、後半は疲れ果ててしまった1年でした。なんと2024年のエントリーは1件だけだったとは……。The Very Long Gameは本全体としては好評のようですが、私にとってはとても苦しい原稿執筆でした。
もう1冊、頼まれていた共著本の原稿を出せなかったのが申し訳ない限りです。最初から書けないと申し上げてはいたものの、最後まで待ってくださっていました。編者の皆様、書けなくてすみませんでした。
今は、学内業務>教育>研究>社会貢献の順なので、あまり対外発信はできていません。いろいろお誘いいただくのですが、参加できないことが多く、残念です。大学院生の新規受け入れもできず、学部の研究会も縮小中です。
それでも暇を見つけては、少しずつ文献を読み、アウトプットもするようにしています。アウトプットが増えると、業務をサボっているのじゃないかと疑われるのがつらいところです。
役職上、大学の同僚の皆さんに「国際共著論文を英語ジャーナルに書いてください」とお願いしている手前、自分でも書いています。恥ずかしながら、査読コメントに対応するのも久しぶりのことで、なかなか集中する時間が取れず、難儀しました。共著者の確認を待っており、それが終わったら査読者に戻します。
社会貢献という意味では、「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」が重要でした。これから法案が国会に出るようです。注目していきます。それぞれあまり会議に出ることができておらず申し訳ないのですが、「経済安全保障法制に関する有識者会議」、「宇宙政策委員会宇宙安全保障部会」、「日米文化教育交流会議(CULCON)」にも可能な範囲で参加を続けます。
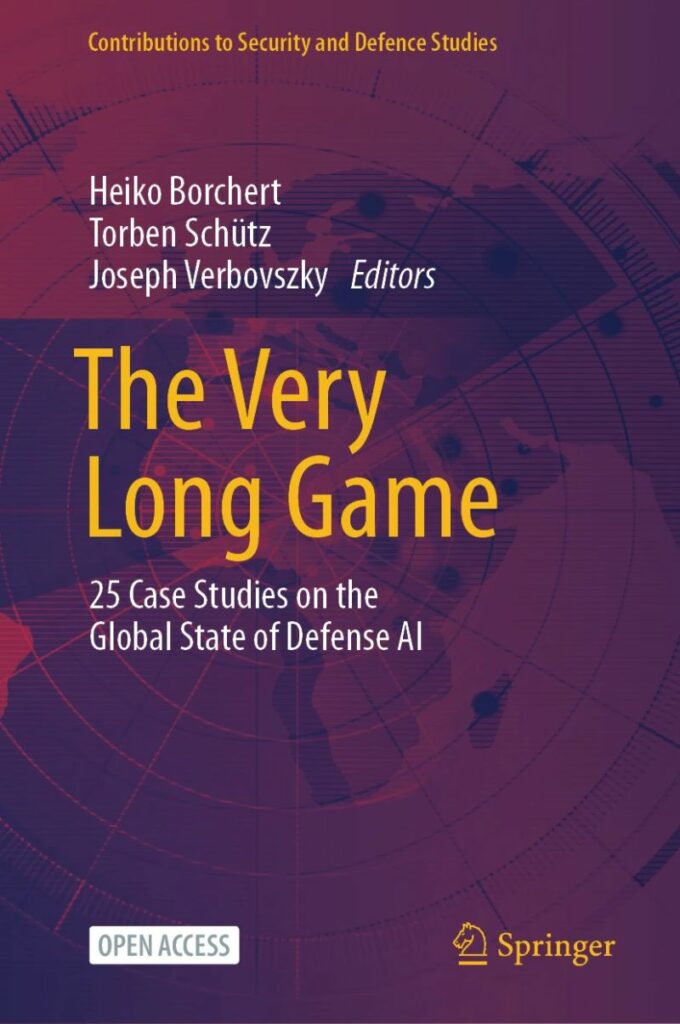
Heiko Borchert, Torben Schütz, and Joseph Verbovszky, eds., The Very Long Game: 25 Case Studies on the Global State of Defense AI, Springer, 2024.
オープンアクセスで全文読めます。私は”Overcoming the Long Shadow of the Past: Defense AI in Japan”というチャプターを書いています。しかし、これを脱稿した後に「防衛省AI活用推進基本方針」が出てしまいました。もうちょっと早く出して欲しかった。
土屋大洋「電池と電波の戦争―情報戦の観点から見たウクライナ侵攻」『月刊経団連』2022年7月号、62〜63頁。
こちらも忘れていました。
土屋大洋「サイバー防衛ここが足りない!」『文藝春秋』2023年2月号、278〜279頁。
書いたのを忘れていましたが、たまたま見つけました。
土屋大洋「U7+アライアンス学長会議開催——平和と安全保障のための教育研究に投資を」『三田評論』第1277号、2023年5月、108〜109頁。
3月16日と17日に三田キャンパスで開催したU7+アライアンス学長会議について報告しています。
岸田首相に東京宣言を手交することもできました。
土屋大洋「中山俊宏君の二冊の本」『三田評論』第1278号、2023年6月、74〜75頁。
中山さんが亡くなってから1年と1ヵ月が経ちました。4月に『理念の国がきしむとき』、5月に『アメリカ知識人の共産党』が出ました。どうぞ読んでください。
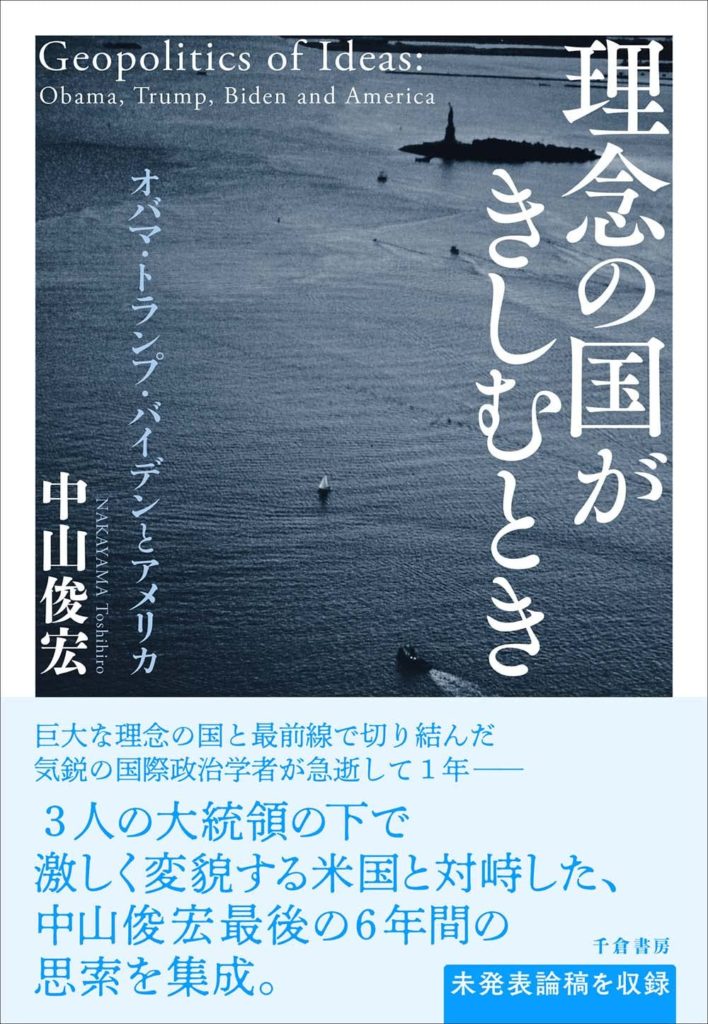
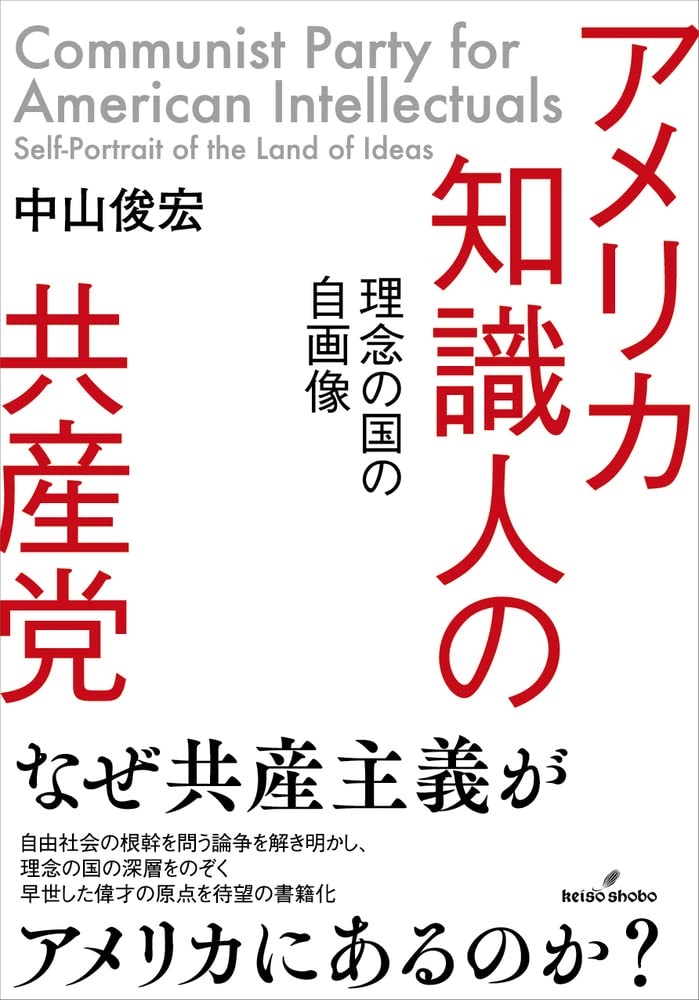
John Bradford, Kristi Govella, Kyoko Hatakeyama, Saadia M. Pekkanen, Setsuko Aoki, James Lewis, and Motohiro Tsuchiya, “Governing the Global Commons: Challenges and Opportunities for US-Japan Cooperation”, German Marshall Fund (GMF), 19 December 2022.
ずいぶん前のことですが、オンライン・イベントを元にした報告書が出ました。Kristiのイニチアチブに感謝です。
土屋大洋「ハイブリッド戦による作戦領域の変化」渡邊啓貴編『トピックからわかる国際政治の基礎知識』芦書房、2023年、64-66頁。
土屋大洋「サイバーグレートゲーム : データをめぐる大国間競争」隊友会編『ディフェンス』第59号、2021年、102-110頁。
土屋大洋「講演 サイバーグレートゲーム : サイバーセキュリティをめぐる大国間競争」『警察学論集』第75巻3号、2022年3月、20-31頁。
土屋大洋「サイバー・宇宙空間・技術のガバナンス」神保謙、廣瀬陽子編『流動する世界秩序とグローバルガバナンス』慶應義塾大学出版会、2023年。
土屋大洋「中山俊宏君を偲ぶ」『三田評論』、2022年7月号。
鈴木一人、土屋大洋「対談 ウクライナ戦争が示す不敗の法則 サイバーや宇宙利用は手段 戦いを決する量・質・外交」『中央公論』第136巻9号、2022年9月、84-95頁。
土屋大洋「米中対立が阻むデジタル投資 太平洋島しょ国支援で」『日本経済新聞』2021年7月27日。
土屋大洋「動き出す国家のサイバー捜査 海外連携、抑止に軸足」『日本経済新聞』2021年9月28日。
土屋大洋「データこそ経済安全保障の要 中国の政策変化に目配りを」『日本経済新聞』2021年11月23日。
土屋大洋「潜水艦探知巡る主要国の暗闘 日本も技術革新に対応を」『日本経済新聞』2022年1月25日。
土屋大洋「侵略国の株奪うサイバー戦 対ロシア、ハッカー巻き込む」『日本経済新聞』2022年3月29日。
土屋大洋「サイバー戦略を見直す契機 認知能力向上が重要に」『日本経済新聞』2022年5月24日。
土屋大洋「データの安全な保管場所 ウクライナは欧州に分散」『日本経済新聞』2022年7月26日。
土屋大洋「権威主義が脅す学問の自由 目障りな研究者を拘束」『日本経済新聞』2022年9月27日。
土屋大洋「民主主義左右する海底通信網 戦時下で繰り返される切断」『日本経済新聞』2022年11月29日。
土屋大洋「偽情報飛び交う台湾選挙戦 中国がもくろむ分断の流れ」『日本経済新聞』2023年1月24日。
土屋大洋「転機迎えるサイバー安全保障 日米、問われる本気度」『日本経済新聞』2023年3月28日。