土屋大洋「サイバー戦場の霧を晴らす」日本国際問題研究所編『国際問題』2017年1・2月合併号。
「安全保障と技術の新展開」という特集号で、以下の皆さんの原稿もセットです。
安全保障の空間的変容 / 鈴木一人
無人化システム・ロボティクスと安全保障 / 神保 謙
技術と安全保障 米国の国防イノベーションにおけるオートノミー導入構想 / 森 聡
ウクライナ危機にみるロシアの介入戦略 ハイブリッド戦略とは何か / 小泉 悠

土屋大洋のブログ
土屋大洋「サイバー戦場の霧を晴らす」日本国際問題研究所編『国際問題』2017年1・2月合併号。
「安全保障と技術の新展開」という特集号で、以下の皆さんの原稿もセットです。
安全保障の空間的変容 / 鈴木一人
無人化システム・ロボティクスと安全保障 / 神保 謙
技術と安全保障 米国の国防イノベーションにおけるオートノミー導入構想 / 森 聡
ウクライナ危機にみるロシアの介入戦略 ハイブリッド戦略とは何か / 小泉 悠
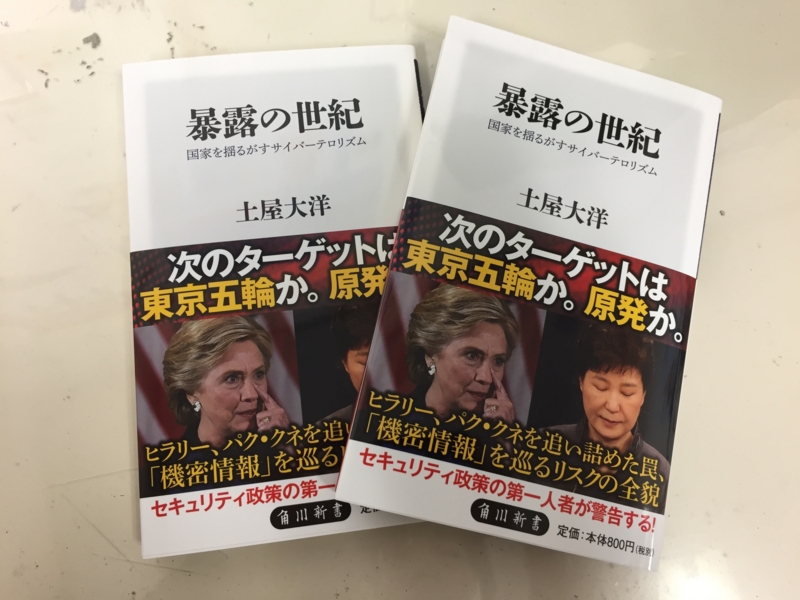
土屋大洋『暴露の世紀 国家を揺るがすサイバーテロリズム』角川新書、2016年。
4月の末にお話をいただいて、夏と秋を使って書き、まとめてきた本が出版された。本当に年内に出るとは思わなかった。
この間、ほとんどブログを更新できなかったが、8月にはハワイのイースト・ウエスト・センターに戻り、原稿のとりまとめと加筆・修正を行う時間がとれた。9月は北京、シンガポール、ベルリン、パリ、ビリニュス(リトアニア)を回ってきた。10月はロンドンのキングス・カレッジ・ロンドンでワークショップに参加した。
この頃から疲れが出て体調が悪くなった。ロンドン行きは、夜遅くに羽田空港まで初校ゲラを届けていただいたが、ひどい風邪を引きながら香港経由で20時間かけてロンドンまで行き、現地で風邪薬が切れてしまい、ひどい状態になった。帰路の香港で、たまらず空港の足裏マッサージに入ってみたら、これが劇的に効いて少し体調が良くなった。
しかし、ロンドンの往復時にチェックするはずだった初校ゲラが進まず、秋学期になって始まった英語の授業の準備にも追われ、11月初めにソウルに行った後にぎっくり腰になった。ここでも再校ゲラのチェックが進まず、どんどん他の仕事が遅れ、今は二つ、締切に遅れている仕事がある。次の出張が来る前に、その二つをどうしても終えておかなくてはいけないが、できる見通しが立たない。
訪問してきた各地でいろいろおもしろいこともあったが、ここで書けなかったのが残念だ。
この本は、これまで出してきた本と少し路線が違う(と本人は思っている)。あまり学問的な裏付けは意識せず、現場重視で書いている。主要参考文献は少し挙げてあるが、脚注は全くない。写真がたくさん入っているが、すべて自前で撮った写真である。水中カメラで撮った海底ケーブルの写真もある。コントラストが弱いので印刷は無理かと思ったが、見事に処理していただいた。
担当してくださったKADOKAWAの皆さんに感謝したい。
めずらしく、たぶん初めて、対談が活字になりました。相手をしてくださったのは、外務省サイバー安全保障政策室の室長の齋藤敦さんです。
土屋大洋、齋藤敦「政府はサイバー空間を守れるか」『外交』第40号、2016年11月、49〜60頁。
Harold, Scott Warren, Martin C. Libicki, Motohiro Tsuchiya, Yurie Ito, Roger Cliff, Ken Jimbo and Yuki Tatsumi. U.S.–Japan Alliance Conference: Strengthening Strategic Cooperation. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF351.html.
3月にサンタモニカのRANDで行われた会議の報告書がまとまったとのこと。半年間、何度もレビューがありました。こういうところから何かを出すのは大変なんですね。
土屋大洋「『パナマ文書』を最初に受け取ったドイツ人記者の手記にみる、「暴露の世紀」の到来」『Newsweek日本版』2016年8月26日。
連載休みと言いながら、『パナマ文書』がおもしろかったので書きました。
土屋大洋「新たな暗号戦争が始まりつつある」『東亜』第589号、2016年7月、6〜7頁。
連載の第3回です。
土屋大洋「スノーデンが暴いた米英の『特別な関係』、さらに深まる」『Newsweek日本版』2016年6月15日。
先日のワシントンDCでのサイバー犯罪シンポジウムに基づくものです。
連載19回目という中途半端ですが、しばらく(少なくとも夏の間は)この連載はお休みになります。
土屋大洋「スノーデン以後のインテリジェンス活動」『治安フォーラム』2016年7月号、39〜46頁。
ある研究会で報告させていただいた話をベースにして、久しぶりに『治安フォーラム』に書かせていただきました。
土屋大洋「狙われる金融機関。日本のコンビニATMとバングラ中銀」『Newsweek日本版』2016年5月30日。
最近遅れ気味のこの連載。締切までに出せないことが多い。関係者の皆様、すみません。
ところで、コラムの本文中でもちょっと触れている通り、バングラデシュ銀行(バングラデシュの中央銀行)の件は、北朝鮮ではないかという報道が出ている。ソニー・ピクチャーズで使われているのと手法が似ているとか。マルウェア自体はブラックマーケットで出回っているものだから、第三者でも使えると思うが、どこまで全体の似ているのだろうか。
2月ぐらいに韓国では、北朝鮮がサイバー攻撃をやりそうだとかなり騒いでいた。国家情報院(NIS)の分析が発信源だったようだ。先日、ソウルに行ったとき、「何かあったのか」と聞いてみると、みんな「そういえば何かあったかなあ」という感じで、大きなものはなかったような感じだった。ところが、この報道が出てきたので、それが正しければ、狙いは韓国ではなく、ニューヨーク連銀(にあるバングラデシュ中央銀行の口座)だったことになる。
これまでの北朝鮮のサイバー攻撃は政治的なデモンストレーションを狙うものが多かった。しかし、今回のは明らかに金銭目的というところが気になる。
北朝鮮の専門家に聞いてみたところ、偽ドル札を作ったこともあるわけだから、やりかねないとのこと。しかし、36年ぶりの党大会の準備をしている最中にそんな下品なサイバー攻撃やるのもどうかなという気がしないでもない。もう少し判断は待ったほうが良いのかもしれない。

Kenji E. Kushida, Yuko Kasuya, and Eiji Kawabata, eds., Information Governance in Japan: Towards a New Comparative Paradigm (SVNJ eBook series), Kindle Edition, 2016.
初めての英語でのKindleバージョン(のような気がする)。私は第8章の”Cyber Security Governance in Japan: Two Strategies and a Basic Law”を担当。
数年かけた共同研究プロジェクトの成果が出たことは喜ばしい。
そして安い! なんと1.98米ドル! 著者たちに印税は入らないってことです。
土屋大洋「サイバー犯罪に取り組むインターポールを訪ねて」『Newsweek日本版』2016年5月9日。
シンガポールでの聞き取り+αに基づく原稿です。
土屋大洋「サイバー攻撃のアトリビューションは魅力的な仕事である」『Newsweek日本版』2016年4月22日。
ここで紹介している論文を読んで、アトリビューションに対する見方がずいぶん変わりました。
土屋大洋「電子戦再考:米陸軍で「サイバー電磁活動」の検討が始まっている」『Newsweek日本版』2016年4月4日。
電子戦についてはちょうどCNNが4月15日付けで「米軍、ISIS掃討に電子戦機投入 通信能力を攻撃か」という記事を出しています。どうなることやら。
土屋大洋「日米サイバーセキュリティ協力の課題」笹川平和財団「日米安全保障専門家会議」報告書、2016年3月。
少し前に公開されていたのを忘れていました。
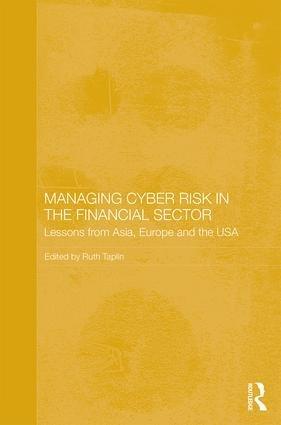
Motohiro Tsuchiya, “Cyber Security of Financial Sectors in Japan, South Korea and China,” Ruth Taplin, ed., Managing Cyber Risk in the Financial Sector: Lessons from Asia, Europe and the USA, London: Routledge, 2016, pp. 96-111.
これも高い本で、95ポンド。今日のレートで15,340円。まあ、ほとんど売れないような気がする。
私は日中韓の金融セクターとのことで、多少、専門分野を超えているのですが、欧米圏の人には分かりにくいだろうということもあって引き受けましたが、けっこう大変でした。
英語で読んでもらえる原稿がしっかりした出版社から出るのは良いことです。
もう一冊、来月にも英語の共著本がweb bookとして出るそうです。ありがたいことです。
土屋大洋「海底ケーブル銀座としての東アジア」『東亜』第583号、2016年4月、6〜7頁。
連載第2回です。
忘れていたリンクを三つ。
土屋大洋「米国政府 vs. アップル 何が問題か:米国議会は法的な穴を埋める立法を検討すべきだ」『webronza』2016年3月22日。
#全文閲覧には登録が必要みたいです。
土屋大洋「サイバー攻撃にさらされる東京オリンピック:時限法も視野に」『Newsweek日本版』2016年3月7日。
土屋大洋「ティム・クックの決断とサイバー軍産複合体の行方」『Newsweek日本版』2016年2月26日。
土屋大洋「サイバーセキュリティ政策をめぐる中国政府の内側」『Newsweek日本版』2016年1月21日。
連載第12回。中国は難しい。本当の黒幕はいるのか、いないのか……。いるほうが分かりやすいのだが……。
学期末の採点で忙しくなっているので、連載はしばらくお休みです。
土屋大洋「NYのダム、ウクライナの変電所…サイバー攻撃で狙われる制御システム」『Newsweek日本版』2016年1月8日。
ウクライナのニュースはもっと日本でも大きく取り上げられても良いはずなのに、日本のメディアは比較的静かな感じがします(フジテレビの夕方のニュース番組で津田大介さんが取り上げておられましたが)。ワシントンDCでのワークショップでは誰もが言及していました。
コラムの前半部分に関連する番組が1月24日(日)夜11時半からNHK(Eテレ)の「サイエンスZERO」で放送されます。制御システムのセキュリティについて解説があります。ちょっと恥ずかしい登場の仕方で、私も出演します。
土屋大洋「サイバーインテリジェンス活動のフロンティア」『東亜』第583号、2016年1月、6〜7頁。
アジアとはあまり関係ない内容なんですが、『東亜』に書かせていただきました。「COMPASS」という連載もので、4ヵ月に1度、執筆機会が回ってくるようです。次は5月号でしょうか。
驚いたことに、ウェブにPDFでそのまま載るんですね。