土屋大洋「テロを恐れつつ、アメリカにも距離を取る多民族国家カナダ」『Newsweek日本版』2015年12月17日。
連載第10回です。年内はこれで終わりです。

土屋大洋のブログ
土屋大洋「テロを恐れつつ、アメリカにも距離を取る多民族国家カナダ」『Newsweek日本版』2015年12月17日。
連載第10回です。年内はこれで終わりです。
土屋大洋「秘密裏だったイギリスのサイバー諜報活動が、オープンに強化される」『Newsweek日本版』2015年11月25日。
ロンドン出張で聞いた話に基づいています。前回の連載の続きといっても良いかもしれません。
土屋大洋「政府機関はテロリストの通信をどこまで傍受していたのか」『Newsweek日本版』2015年11月19日。
連載の第7回。急遽、内容を変更して掲載してもらいました。
テロが起きたとき、私はロンドンから東京に戻る機内の中でした。飛行機に乗る前のヒースロー空港で見たテレビではたいしたニュースをやっていなかったのに、帰国したら世界が変わっていたという感じです。
イギリスのオズボーン財務大臣が政府通信本部(GCHQ)を訪問しているときの写真がリンク先にあります。こんな感じなんですね。テロの後にオズボーン財務大臣がGCHQを訪問してハッパをかけたときの写真でしょう。
オズボーン財務大臣は先の英中首脳会談に際して親中派と日本のメディアでは報じられましたが、将来の首相候補でもあり、注目の人とロンドンで教えてもらいました。
最初、チャンセラーと何度もイギリス人が言うので分からなかったのですが、イギリスの財務大臣はチャンセラー(chancellor)というのだそうです。チャンセラーはドイツでは首相なので混乱します。大学では総長の意味で使うこともあります。
土屋大洋「この一冊 インターネットガバナンス ローラ・デナルディス著 管理の課題、多様な視点から解説」『日本経済新聞』2015年11月15日。
日曜日の日経書評欄に『インターネットガバナンス』の書評を載せてもらう。原稿はロンドンに行く前に書き、ロンドン滞在中に最終のゲラ確認を行った。
最初は気づいていなかったが、後で著者のローラ・デナルディスには会ったことがあることを思い出した。2009年2月、ボストン滞在中にイェールでのセミナー発表に呼んでくれたのだ。雪嵐が来ていて、イェール滞在はゆっくりできず、デナルディスとも挨拶程度で終わってしまったので、彼女は私のことは覚えていないだろう。今は同プロジェクトのAffiliated Fellowになっているようだ。
書評そのものには十分に書き切れなかったが、第9章の「インターネットガバナンスの暗黒技法」は今の私の関心からしてかなりおもしろい。政治に翻弄されるインターネットの自由を垣間見ることができる。
ロンドンからの帰国便ではおもしろい映画がなかったので、ベン・マッキンタイアー(小林朋則訳)『キム・フィルビー』(中央公論新社、2015年)を読み始めた。眠ってしまったのでまだ半分しか読めていないが、おもしろい。なぜ彼が「キム」と呼ばれるのか理解できないでいたが、父親が付けたニックネームのようだ。
イギリス社会は魅力的だが、当時の社会的風潮と教育システムが、フィルビーのような複雑な人格を作り出してしまったかと思うと考えさせられるものがある。たくさんのイギリス人と話してきた後でこの本を読むと味わい深い。
そうそう、ロンドンでは『SPECTRE』が公開されていたが、観る時間がなかった。イギリスでこそ観たかった。残念だ。
角川インターネット講座全15巻が完結したそうです。私が担当した第13巻は昨年末に出てしまいましたから、ずいぶん時間が経った感があります。完結を機にプロモーションビデオができたそうです。私のプロフィール写真はいまいち評判が悪く(海外にいたのでそこら辺で撮った写真を使っていました)、このたびカドカワのプロの方に撮っていただいたところ、その写真がビデオに使われ、ちょっと恥ずかしい感じのポーズです。ご笑覧ください。
ascii.jpで連載も始まるそうです。
社長と働き盛りの30代に読んで欲しいシリーズが完結!仕掛け人に話を訊いた – 週刊アスキー
さらに、「無料お試し版&合本版電子書籍」も出たそうです。
【無料お試し版】角川インターネット講座 各巻序章完全収録(最新刊) – 実用 村井純(角川学芸出版全集):電子書籍ストア – BOOK☆WALKER –
土屋大洋「ロシアの潜水艦が米国の海底ケーブルの遮断を計画?」『Newsweek日本版』2015年10月27日。
海底ケーブルが狙われるという話は、常々考えてきたわけですが、いよいよ来てしまったかという感じがします。
通常は隔週で書いていますが、私の都合で次回は3週間後です。
土屋大洋「日本は、サイバー・ハルマゲドンを待つべきか」『Newsweek日本版』2015年10月15日。
この連載は原稿を送るとぱっと載ってしまうので、なんとも怖いものがあります。
土屋大洋「通信拠点として見るハワイの戦略的重要性」『公明』2015年11月号、52〜57頁。
書き切れなかった感はありますが、なぜハワイに行ったのか、言い訳的に書いた原稿です。インチキな点はプロフィールの写真で、15年ぐらい前のものです。ゲラの確認が出張と学期はじめと重なってしまい、写真を差し替える時間がありませんでした。まあ、許してもらいましょう。念のためですが、媒体は支持政党を示唆するためのものではありません。
土屋大洋「意外だが、よく分かる米中のサイバー合意」『Newsweek日本版』2015年9月28日。
先月末に公開になったコラムです。
土屋大洋「国連を舞台に、サイバースペースをめぐって大国が静かにぶつかる」『Newsweek日本版』2015年9月15日。
出張に行っている間に公開になっていました。
土屋大洋「年金情報流出とサイバーセキュリティ戦略—「共有」と「連携」の新戦略—」nippon.com、2015年9月3日。
たまたま時期が重なりましたが、こちらも公開されました。
土屋大洋「サイバー攻撃で、ドイツの製鋼所が甚大な被害を被っていた」『Newsweek日本版』2015年9月1日。
日本語でもニュースで流れた事例なので、新しいわけではありませんが、それなりにびっくりした事例なので、取り上げました。
文中で取り上げたBSIの報告書は以下にあります。
また、引用しているドラゴス・セキュリティのブログ・エントリーは以下にあります。BSIの報告書はドイツ語ですが、このブログ・エントリーに英訳があります。
https://dragossecurity.com/blog/9-ics-cyber-attack-on-german-steelworks-facility-and-lessons-learned
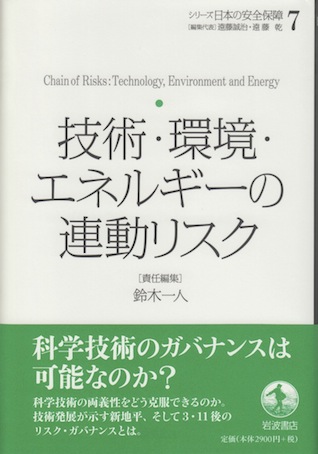
土屋大洋「サイバーセキュリティ」鈴木一人編『技術・環境・エネルギーの連動リスク』岩波書店、2015年、235〜253頁。
シリーズ日本の安全保障の第7巻。久しぶりの岩波書店。以前担当してくれたIさんは退職されて、今回は清水野亜さんが編集担当。
第8巻のグローバル・コモンズに呼ばれたのかと思ったら、技術の第7巻だった。
同僚の蟹江憲史が第4章に「地球システムと化石燃料のリスクガバナンス」を書いている。注目しているのは第7章の加藤朗先生による「ウォーボットの戦争」。おもしろそう(編者と編集者以外は他章の内容を事前には読んでいない)。
そして、気が付くと、出版待ちになっている残りの共著本はあと3冊で、いずれも英語。この1冊は間違いなく来年出るだろう。しかし、160ドルという価格設定がすごい。誰が買うのか。きっと私への印税はゼロで、印税が出るとすれば編者が総取りなんだろう。
2冊目は、すでに2年ぐらい棚晒しで、どうなっているのか分からない。聞けば「出る」と言われるのだが、著者が日本人ばかりなので難しいのだろう。3冊目は、今年の3月に原稿を出したものの、その後、編者に変更があったらしく、音沙汰がない。共有しているフォルダは4月以降誰も触っていないようだ。
他の本はまだ模索中。原稿はおろか、出版社も決まらず、企画も確定していない。のんびり行きましょう。
土屋大洋「サイバー攻撃が、現実空間に大被害をもたらしたと疑われる二つの事例」『Newsweek日本版』2015年8月20日。
その昔、ホットワイアード・ジャパンというオンラインメディアで連載の機会をいただいたことがあります。その時の縁でNewsweek日本版のオンラインで連載をさせていただくことになりました。短いものを頻繁にという編集方針のようなんですが、途中で息が続かなくなるかもしれません。
日本国際問題研究所の米中関係の研究会に入れてもらっています。関連するコラムを書きました。
土屋大洋「中国のサイバーセキュリティをめぐる霧」日本国際問題研究所編『US-China Relations Report』Vol. 1、2015年8月5日。
私は中国研究者ではありませんが、サイバーセキュリティをやっているとどうしても中国のことを見なくてはいけないので、この研究会で中国研究者の皆さんに教えてもらっています。
梅本哲也先生のコラム「米中の対外戦略と『安全保障のジレンマ』」も同時に出ています(上のリンクからたどれます)。
土屋大洋「民主主義体制とインテリジェンス活動」『治安フォーラム』2015年7月号、64〜67頁。
連載「インターネットとインテリジェンス」は第20回にして最終回となりました。2013年7月号から続き、途中で飛び飛びになりましたが、2年にわたって続きました。
編集長はじめ編集部の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。読者の皆様にも御礼申し上げます。
土屋大洋「グローバル・コモンズとしてのサイバースペースの課題」日本国際問題研究所編『平成26年度外務省外交・安全保障調査研究事業(調査研究事業)「グローバル・コモンズ(サイバー空間、宇宙、北極海)における日米同盟の新しい課題」』2015年、27〜37頁。
昨年度の報告書が公開されました。私の担当箇所は、サイバーセキュリティというよりは、サイバースペース全体にかかわる課題でしたので、少しぼんやりとした話になっているかもしれません。私の担当箇所では具体的な提言が入っていないので申し訳ないです。
土屋大洋「サイバーインテリジェンス」『治安フォーラム』2015年6月号、63〜66頁。
連載19回目。昨年中に書いた原稿ですが、編集部の都合で掲載がとびとびになっているため、ようやく掲載になりました。次回の20回目が最終回の予定です。
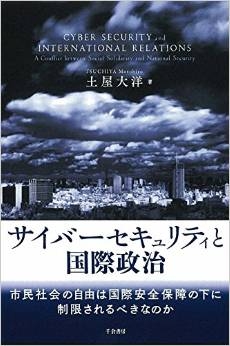
土屋大洋『サイバーセキュリティと国際政治』千倉書房、2015年。
『仮想戦争の終わり』(KADOKAWA、2014年)が昨年末に出たばかりなので、「またか」という声もあるが、単著本としては『サイバー・テロ 日米vs.中国』(文春新書、2012年)以来なので3年ぶりになる。
前著を出してからの一番大きな関心事はエドワード・スノーデンの問題であり、米国家安全保障局(NSA)については2001年の9.11以来追いかけてきたことでもあるので、米英の反応を中心にまとめたのが本書である。
ハワイのイースト・ウエスト・センターにいる間の昨年5月末に最初のドラフトを提出した。しかし、その後もいろいろなことが次々と起こるので、何度も加筆・修正を行い、ようやく出版にこぎ着けた。
今回はKDDI財団から寛大な出版助成をいただくことができたため、発行部数は少ないが、値段はそれほど高くなっていない。この出版助成は、KDDI総研が発行している『Nextcom』という雑誌に論文などを書くと申請資格が得られ、KDDI総研から推薦してもらうという枠組みになっている。私も知らなかったのだが、某先生からずいぶん前に教えてもらい、機会を狙っていた。幸い、審査を経て助成をいただくことができた。関係各位に感謝したい。
『サイバーセキュリティと国際政治』のおもしろいところは、編集担当の神谷竜介さんが頑張ってくださり、装丁の米谷豪さんとともに、とても印象的な表紙および装丁を作ってくださったことだ。米谷さんは拙著『ネットワーク・パワー』(NTT出版、2007年)でも印象的なオレンジの表紙を作ってくださっている。『サイバーセキュリティと国際政治』では神谷さんと米谷さんが、写真家の橋本タカキさんに掛け合ってくださり、橋本さんはたくさんの写真をこの本のために提供してくださった。この写真の意味するところは『サイバーセキュリティと国際政治』の「はじめに」に書いてあるので参照いただきたい。神谷さん、米谷さん、橋本さん、ありがとうございます! 千倉書房の皆さんにも御礼申し上げます。
千倉書房はもともと経営学の出版社として知られていたが、神谷さんが編集部長になられてから、政治学、国際政治学、歴史学分野の発行が充実してきている。これらの分野の研究者なら本棚に1冊、千倉書房の本が入っていてもおかしくない。これから出版をと考えている方にはお薦めしたい。千倉書房は一説によると東京駅に最も近い出版社だそうである。
土屋大洋「サイバーセキュリティ基本法の成立と組織改革」『治安フォーラム』2015年5月号、48〜51頁。
連載第18回です。