土屋大洋「サイバー攻撃を受け、被害が出ることを前提に考える「レジリエンス」が重要だ」『Newsweek日本版』2018年5月10日。
こちらもすぐに出ました。

土屋大洋のブログ
土屋大洋「サイバー攻撃を受け、被害が出ることを前提に考える「レジリエンス」が重要だ」『Newsweek日本版』2018年5月10日。
こちらもすぐに出ました。
土屋大洋「ついに行われた米国サイバー軍の昇格 自衛隊はついていけるのか」『Newsweek日本版』2018年5月10日。
久しぶりに載せていただけました。
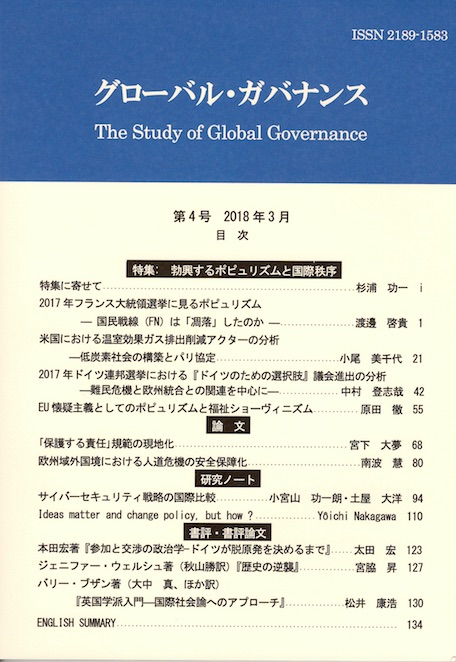
小宮山功一朗、土屋大洋「サイバーセキュリティ戦略の国際比較—目的と対象範囲に基づく四類型—」グローバル・ガバナンス学会編『グローバル・ガバナンス』第4号、2018年3月、94〜109頁。
研究ノートとして採録されました。各国で出ているサイバーセキュリティ戦略を並べてみると何が言えるかを考えたものです。
今週末、京都の同志社大学で開かれます。
******
グローバル・ガバナンス学会編『グローバル・ガバナンス学 Ⅰ・Ⅱ』(法律文化社)刊行記念シンポジウム&ワークショップ
日時:2018年3月17日(土)13時〜15時30分
テーマ:「グローバル・ガバナンス学の可能性」
目的:グローバル・ガバナンス学会設立5周年を記念した本叢書の刊行を受け、以下の各報告者が、執筆章の観点を交えつつ、それぞれの「グローバル・ガバナンス学」の可能性を議論し、展望します。
司会:松井康浩(九州大学)
第1部:
〔以上、第1巻より〕
第2部:
総括報告:
〔以上、第2巻より〕
その後、総括討議 司会:松井康浩(九州大学)・福田耕治(早稲田大学)
3月2日、米国太平洋軍(USPACOM)に関するシンポジウムを慶應の三田キャンパスで開催します。どうぞご来場ください。

Motohiro Tsuchiya, “Systematic Government Access to Private-Sector Data in Japan,” Fred H. Cate and James X. Dempsey, eds., Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, Oxford University Press, 2017, Chapter 13.
ふと思い出して調べてみたら、書いた原稿が本になっていました。見本を送ってくれるというから待っていたのですが、そのうちに忘れていました。なんで送ってくれないのでしょう。
ただし、これは前に書いたジャーナルの論文にいくつか修正をしたものが採録されているので、完全に新しいものではありません。
それに高い!
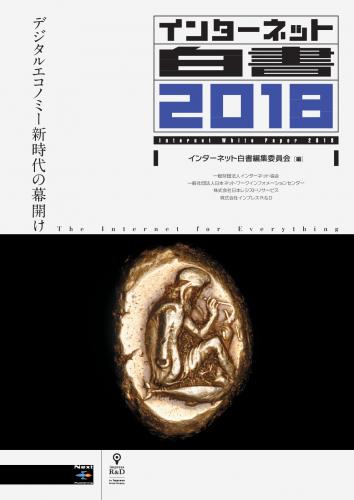
土屋大洋「国際政治とサイバー攻撃」インターネット白書編集委員会編『インターネット白書2018』インプレスR&D、2018年、265〜268頁。
年末にInternet Week 2017に呼んでいただいたご縁で、『インターネット白書2018』に4ページ書かせていただきました。たぶん、普段とは違う読者の皆さんなので、どう受け止められるか、楽しみでもあり、心配でもあります。

土屋大洋「サイバーセキュリティ」グローバル・ガバナンス学会編、渡邊啓貴・ 福田耕治・ 首藤もと子責任編集『グローバル・ガバナンス学II』法律文化社、2018年、203〜220頁。
気がついたら年が明けて1カ月以上経っていて、このブログは何も更新しないままでした。年末年始は外に出ない報告書原稿や出張で忙しく、何も外向けの原稿を書いていなかったいうことですね。
そんなとき、昨年書いていたグローバル・ガバナンス学会の叢書が届きました。2冊セットで、私はIIのほうに1章書かせてもらいました。
内容としては、以下の本で書いてきたことの延長にあり、インターネットをめぐるガバナンスがどう変わってきたか、特に近年のサイバーセキュリティでどう変わってきたかということです。
土屋大洋「不安定さを増すサイバーガバナンス」『東亜』2017年10月号、6〜7頁。
載せるのを忘れていました。
土屋大洋「ルーマニアに見るサイバーセキュリティの地政学と地経学」『治安フォーラム』2018年1月号、66〜69頁。
ひええー、ついに2018年!
土屋大洋「ロシアでサイバーセキュリティが議論されない理由」『Newsweek日本版』2017年12月25日。
25年ぶりにロシアに行ってきました。ずいぶん変わっていました。
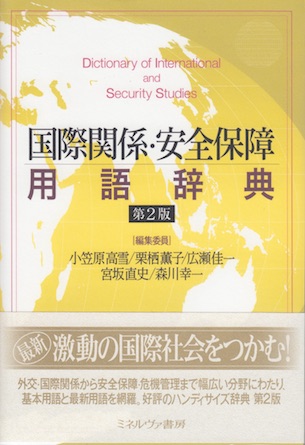
小笠原高雪、栗栖薫子、広瀬佳一、宮坂直史、森川幸一編『国際関係・安全保障用語辞典 第2版』ミネルヴァ書房、2017年。
今どき、第2版が出るなんていうのはめずらしいことですが、2013年初版の『国際関係・安全保障用語辞典』の第2版が出ました。
私は「インテリジェンス」「インテリジェンス・コミュニティ」「サイバー攻撃」「サイバーセキュリティ」を担当しました。
総勢33人で執筆しており、同僚の中山俊宏さんと神保謙さんも参加しています。
土屋大洋「ハックされた世界秩序とサイバー・ドラゴンの台頭」『Newsweek日本版』2017年11月1日。
ファンタジー映画のタイトルみたいですが……。
土屋大洋「IoT(Internet of Things)の次、IoB(Internet of Bodies)への警告」『Newsweek日本版』2017年9月28日。
原稿がアップロードされるまで知らなかったのですが、映画『ザ・サークル』の試写会をNewsweek日本版編集部が募集しています。私は飛行機の中でたまたま見てしまいました。
土屋大洋「サイバー攻撃を押しとどめる抑止理論はまだ見つからない」『Newsweek日本版』2017年9月20日。
こちらは9月はじめのソウル防衛対話に基づく話です。
土屋大洋「在日米軍より強大「太平洋軍」の役割と任務を知っていますか:9つの統合軍のうち最大規模」『現代ビジネス』2017年9月20日。
ハワイの太平洋軍について、概略的な原稿を載せていただきました。

田中 明彦、日本経済研究センター編『提言 日米同盟を組み直す 東アジアリスクと安全保障改革』日本経済新聞出版社、2017年。
月末に発売です。私は「第7章 サイバー安全保障と日米インテリジェンス連携」(139〜151頁)を担当しています。あまり部数を刷らない上に、某会合でたくさん配布してしまうらしいので、あまり市中には出回らないかもしれません。
目次
わがSFCには特別研究プロジェクトという制度があり、夏休みや春休みに国内外で集中授業を行うと単位が付く。私は今までやってことがなかったが、たまたま日程がうまく空いたので、初めて8月上旬に実施した。10人の学部学生とともに台湾を訪問し、安全保障と文化における日台協力について学んだ。
田中靖人・産経新聞台北支局長(SFC出身)にレクチャーをお願いしたり、台湾師範大学でもレクチャーをお願いしたりした。


有名な誠品書店を訪問すると確かに日本の本や雑誌が置いてある。写真は子供用のセット。台湾の子供もこういうのを買うのだろうか。それとも現地在住の日本人向け?

私の個人的な調査対象としては淡水という街にある海底ケーブル陸揚局。



中国語(繁体字)で海底ケーブルは「海底電纜」、陸揚局は「海纜站」というらしい。
最終日の午後に国立政治大学で成果報告会を開き、コメントをいただいた。日台協力というのは簡単だけど、具体的に何ができるかと考えるととても難しい。お互いの文化が気に入って旅行しているだけではほとんど何も改善しない。それをひとまずは学生たちが認識してくれたようなので、ひとまず良かったことにしよう。

もちろん、合間にはおいしい料理もいただいた。写真は学部の時の同級生に連れて行ってもらった居酒屋での宴会料理。シジミの醤油漬け老酔蜆子がどこでもおいしい。

土屋大洋「サイバーセキュリティの地政学」『ITUジャーナル』2017年9月号、21〜23頁。
期間限定で全文読めるそうです。
大学院生の頃は、どうやったらこの雑誌に書かせてもらえるのだろうと思っていたのに、突然あっさりと執筆依頼が来て、その割に書くのに苦労してしまいました。3ページ目に大きな空白が空いているのは、たぶん私が図を入れなかったからです。
2014年から15年にかけてハワイのイーストウエストセンター(EWC)に客員研究員として置いてもらい、それはそれで充実した研究の時間をもらえて良かったのだけど、新しい研究テーマとして太平洋軍(PACOM)を見つけて来た。
それから年に一、二度、ハワイに通い、太平洋軍の研究プロジェクトを行ってきた。その一環として、8月22日に小さなシンポジウムをEWCで実施させてもらった。

キーノートは元太平洋艦隊司令官のAdm. R.J. ”Zap” Zlatoperで、率直にPACOMについて教えてくださった。日本からは元海上自衛隊の中村進さん、日本国際問題研究所の小谷哲男さん、慶應法学部の西野純也さんに来てもらった。
アメリカ側からは他におなじみのBrad Glossermanさん(もうすぐ日本で仕事を始めるそうだ)、朝鮮半島の専門家のKevin Shepardさん、プロジェクトのメンバーのEWCのDenny Royさんが参加してくれた。
三澤康ホノルル総領事とRichard Vuylsteke EWC所長もご挨拶をしてくださった。
PACOMの現役の軍人も参加してくれて、小さいながらも良いシンポジウムだった。アジェンダはこちら。
ところで、この翌日、PACOMを訪問して意見交換をする機会をいただいたのだが、帰り道、高速道路でタイヤがパンクするというアクシデント。運転中に何か変な音がするなと思ったら急にガタガタガターと音がして慌てて路肩に止める。右前輪のゴムの部分が完全に外れて、高速道路の後ろのほうに転がっている。後続の車がよけながら走っていて危ない。初めての経験でオロオロしてしまったが、ハイウェイパトロールのおじさんがやってきて、あっという間に直してくれた。誰もけがをしなかったので良かった。
2014年の滞在中、パリ・ハイウェイを走っていたら2台前の車が、対向車と正面衝突し、炎上するという事故も見たことがある。ハワイの運転はよくよく気をつけないと。