土屋大洋『サイバーグレートゲーム—政治・経済・技術とデータをめぐる地政学—』千倉書房、2020年。
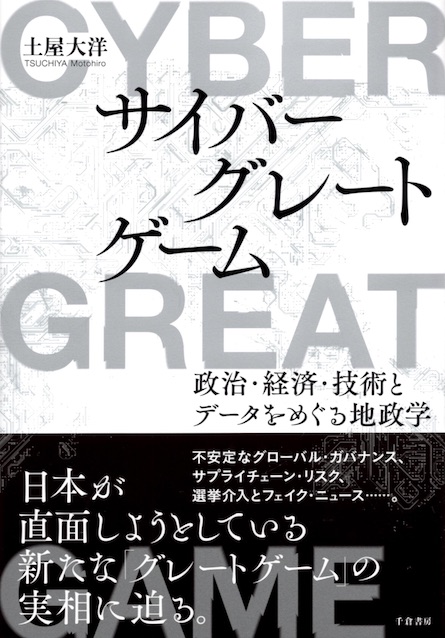
4年ぶりに単著を出版していただきました。編集は神谷竜介さん、装丁は米谷豪さんです。お二人にはこれまでも何度もお世話になってきました。神谷さんには『海洋国家としてのアメリカ』『サイバーセキュリティと国際政治』『アメリカ太平洋軍の研究』をお願いしてきました。米谷さんには『ネットワーク・パワー』『サイバーセキュリティと国際政治』『アメリカ太平洋軍の研究』でお世話になりました。今回もありがとうございます。
この本の原稿は、2018年の春からまとめ始めました。4月から9月までサバティカル(研究休暇)をいただき、三田キャンパスのグローバルリサーチインスティテュート(KGRI)に籠もっていました。しかし、なかなか進まず、ズルズルと時間が経ち、そうこうしているうちに忙しくなり、今日になってしまいました。
サイバーセキュリティとなると、パソコンの前に座っていれば分かるという感じがあるかもしれませんが、実際には国際政治の一環であり、インテリジェンス活動の一環でもあります。インターネット上に文字として表現されない、画像や動画として表現されないことがあり、それを見聞きし、感じ取るためには、現場に行かなくてはならないこともあります。2016年12月に『暴露の世紀』を出していただいて以来、見聞きし、考えたことが詰まっています。各所で撮った写真も入れてもらいました。
無論、直近の9ヶ月間はどこにも行っていませんし、新型コロナウイルス対策に追われてきたわけですが、しかし、どこにも行かなかったがゆえに、まとめられたという気もします。
目次
第1章 サイバーセキュリティにおける予期と特定
第2章 統合される作戦領域
第3章 選挙介入とフェイク・ニュース
第4章 サプライチェーン・リスク
第5章 サイバーインテリジェンス
第6章 サイバー外交
第7章 サイバー防衛
第8章 狙われる日本
「サイバーグレートゲーム」というタイトルは、日本経済新聞に載せていただいたコラム「現代のグレート・ゲーム データ資産をめぐる争奪戦」(2020年7月29日)から取っています。2019年4月から毎月、「中外時評」欄に書かせていただいています。
「あとがき」で感謝すべき方々のお名前を挙げていますが、いつも忘れている人がいるのではと心配になります。多くの方々のお世話になっています。ありがとうございます。
追記:大変申し訳ないことに、手違いで古い略歴がこの本には掲載されています。すでに慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)の副所長は退任し、上席所員に変わっています。大変申し訳ありません。
修正点:今のところ以下の修正点が見つかっています。
- 15ページ 下から3行目 「その指令と当時に」→「その指令と同時に」
- 56ページ 11行目 「あるいはDNC」→「あるいは民主党全国委員会(DNC)」
- 56ページ 18行目 「民主党全国委員会(DNC)から」→「DNCから」
- 56ページ 21行目 「日本経済新聞出版社」→「日本経済新聞出版」
- 127ページ 14行目 「サイバーネットワーク防衛(CND)」→「コンピュータネットワーク防衛(CND)」

