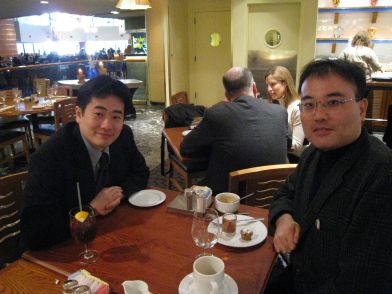アメリカではクリスマスはほとんどの仕事が休みになる。レストランもほぼ全部休みになり、日本のようにクリスマス・ディナーや忘年会で盛り上がることはない。ほとんど人も出歩かず、道路もすいている。一つの宗教に基づく休日は政教分離に反するのではないかと思うが、とにかくほとんどの人が仕事をしない。サンクスギビングは友人・知人を呼んでパーティーという人が多いが、クリスマスは家族水入らずというところが多いような気がする。クリスマス・イブはラストミニッツの買い物客がいるが、クリスマスになると街はとても静かだ。
CVSという薬局兼雑貨屋は開いているというので、デジカメの写真を印刷しに行った。隣にあるダンキン・ドーナッツも開いていて、かなり人が入っていた。他に行くところがないのだろう。CVSにはキヨスク端末が置かれていて、自分でデジカメの写真を印刷できる。これまでも何回かやっていて問題なかったので、今回も大丈夫だろうと踏んでいた。CVSの店内も、いつもよりも人が入っている気がする。やはり他に行くところがないのだから、案外かき入れ時かもしれない。
キヨスクはいつも通りの様子だったので、タッチスクリーン式の画面で写真と枚数を指定して、印刷の注文を出した。普通なら1分以内に写真が出てくる。しかし、今回は出てこない。画面を見ると、小さなエラーマークが出ているので、クリックすると、「インクリボンがない」と出ている。近くにいた店員に、「インクリボンがないと出ているのだけど、直してもらえますか」と聞いた。
「それ、今日は動いてないから。」でたでた、アメリカ的対応である。「機械は動いているし、注文しちゃったよ。」「担当者がいないから。」これもアメリカ的。「じゃあ、どうやってキャンセルするの。」「ワン・セカンド」といってその人は店の裏へと消えていく。しかし、待てど暮らせど帰ってこない。これもアメリカ的。
仕方ないので、別の人をつかまえて同じことの繰り返し。その彼は店の裏へと消える代わりに、「チッ」と舌打ちをした後、カギを取り出してキヨスクを開け、リボンの交換を始める。これもアメリカ的。こちらも黙って作業させる。すると、先ほど店の裏へ消えた男が、着替えて何知らぬ顔で帰っていく。これもまたアメリカ的。
作業を終えた男はばたんとキヨスクを閉めてあっちへ行ってしまう。写真がバラバラと出てくる。時間はかかったが目的は達したのでよしとしよう。クリスマスに仕事している彼らも楽しくはないのだろう。
今日の教訓:アメリカのクリスマスは家でおとなしくしているべし。
こんなことがあってから家に帰って、トーマス・フリードマンのクリスマス・イブのコラムを読むと、「アメリカをリブートせよ」と言っている。アメリカには才能ある人が集まっているけど、インフラストラクチャもサービスも全然ダメじゃないかと言っている。その通りだと叫びたくなる。
CVSのキヨスクと同じで、便利なものを設置したのは良いものの、ちゃんとメンテナンスが行われないで放置されている社会インフラストラクチャが多すぎる。道路や電車、空港、建物、みんなそうだ。古いものが良いとされるのはイギリスに任せておいた方が良い。歴史の長さが違うのだから。アメリカは金ピカで新しい方が似合う。アメリカは疲れてしまっている気がしてならない。
そして、サービスも悪すぎる。ワシントンDCに住んでいる人は、ボストンの店員がにこやかだと驚く。確かにそうだ。しかし、ボストンでもCVSの店員のようなのはゴロゴロいる。チップをもらえるレストランやホテルの従業員だけがきびきび動く。
先日の東京のシンポジウムでこうした点を批判したら、私は日本での生活にスポイルされているというコメントを頂戴した。日本のクオリティは確かに高すぎるかもしれない。しかし、アメリカが期待よりもただ低いのだと思う。アジアの都市では(暑いのと人が多いのをのぞけば)もっと快適に過ごすことができる。
アメリカは世界一の国だとアメリカ人は言うが、必ずしもそうだとは思えない。フリードマンが別のコラムで書いているとおり、もうアメリカと中国の差はぼけてきている。自慢の資本主義も政府の助力がないとダメになってしまった。他国の産業が政府に保護されているのを批判していたのだから、アメリカの自動車会社をアメリカ政府が救済するのは筋が通らない。エンロンのような不正会計があったと思ったら、マドフ・ファンドのようなネズミ講が社会的信用のある人によっておおっぴらに行われていた。
アメリカは本当にリブートすべきだと思う。よれよれになった社会をさっぱりと新調して欲しい。オバマ大統領就任まであと1カ月足らず。期待しすぎてはいけないと思いつつ、期待してしまう。
とここまで書いて、ブログに上げるのが面倒で放置していた。そして、クリスマス明けに近所のスーパーで買い物。翌日、大学時代の友人夫婦が自宅に来るので準備を開始したところ、買ったはずの品物が見あたらない。レシートを確認すると確かに支払っている。このスーパーでは商品を店員が袋に入れてくれるのだが、入れ忘れたようだ。リターン(返品)はありだとしても、入ってなかった(と客が主張する)商品はどうなるのだろう。
このまま泣き寝入りも悔しいので、レシートを持ち、スーパーに戻った。入っていなかった商品を手に取り、カスタマー・サービスへ。「こんにちは。」「こんにちは。どうされましたか。」「昨日、ここで買い物をして、この商品の支払いをしたのですが、家に帰ったら袋にこの商品が入っていませんでした。」「ああ、そうですか。今日はこれからまたお買い物ですか。」「いいえ、今日はもう買い物はありません。」「それでは、どうぞ。」と出口を指さされた。
ううむ。こちらの言い分を100%聞いてくれたのはありがたいが、いいんだろうか。レシートすら確認しようとしなかった。アメリカ経済が本当に心配になる。