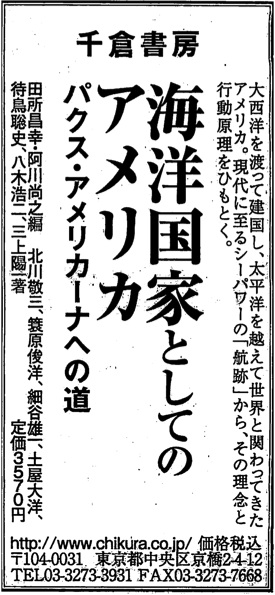
2013年11月8日付けの日経1面に載った千倉書房の広告です。記念に載せておきます。
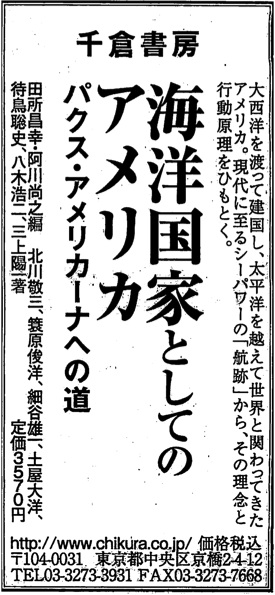
2013年11月8日付けの日経1面に載った千倉書房の広告です。記念に載せておきます。
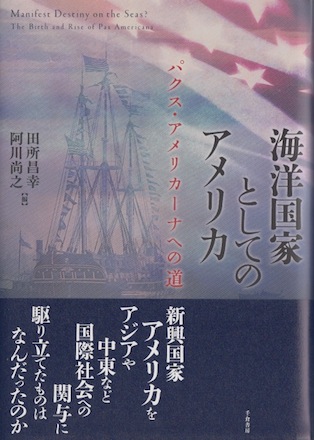
田所昌幸、阿川尚之編『海洋国家としてのアメリカ―パクス・アメリカーナへの道―』千倉書房、2013年。
第6章「海底ケーブルと通信覇権」149〜174頁を担当しました。
サントリー文化財団で行われた研究会の成果です。
韓国の先生と雑談していたら、「e知園」の問題が韓国で議論になっているという。「e知園」なんて聞いたことなかった。何なんだろう。
忘れないようにひとまずメモ。
久しぶりの韓国・ソウル。今回は国民大学校とのシンポジウム。私はコメンテーターなので、それほどの準備はいらない。
こうしたシンポジウムでの意見交換は、それはそれでおもしろいが、本音の議論は懇親会の席で行われると言っても過言ではない。
しかし、アジア、特に韓国と中国の懇親会はすさまじい。韓国では爆弾酒がどんどん出てくる。
今回、私はいろいろな役が解けて解放感があったせいか、隣の中国の先生のあおりがすごかったせいか、久しぶりにひどく酔ってしまい、ひとりだけ一次会で退散。同僚たちは二次会、三次会へと繰り出したらしい。
私はつくづく地域研究者ではなくて良かったと思う。毎回こんな飲み会が続いていたら、必ず体調に異変を来しただろう。隣に座った中国人の先生は、韓国に留学していたそうだが、そのときには少ない時で週に4回、多いときは6回の飲み会があったそうだ。
私が自分の研究で海外に行くときには、飲み会に行く回数はぐっと少ないし、行ったとしても手酌で飲みたいだけ飲めば良い。無理強いされることはない。
アジアでは、どれだけ一緒に酒を飲んだか、どれだけ一緒に羽目を外したかが問われるところがある。その思い出が信頼となる。
しかし、私には無理だ。それを改めて実感した夜だった。
学部生の頃、ロシア研究のゼミに入ろうと思ったことがあったが、そこに入っていたら、体力が続かなくて、私は研究者にはなっていなかっただろう。
個人的な事情があって、10月6日の任期満了をもって、情報セキュリティ政策会議を退任しました。
2期4年務めさせていただきましたが、とても貴重な機会でした。
この会議で機密情報にアクセスしていると勘違いされることもありましたが、そんなことはありません。この会議で出てくる資料はすべて内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)のウェブページで公開されています。議事要旨も公開されています。
それでも、会議のメンバーであるということは、さまざまな政策決定の文脈を理解する機会があるということであり、日本政府の情報セキュリティないしサイバーセキュリティ政策が議論されるプロセスの理解にはとても役に立ちました。サイバーセキュリティだけでなく、政治システムの理解という意味でも、興味深い4年間でした。
しかし、個人的には忙しすぎる4年間でした。この会議に任命を受けたのが2009年8月、その翌月からは総合政策学部の学部長補佐、グローバルセキュリティ研究所(G-SEC)の副所長の仕事も始まったので、会議漬けの4年間でした。本当に多かった。合計すると何時間会議室に座っていたことか。
この三つの仕事が9月末から先週にかけて、すべて退任になり、重荷を下ろした気分です。
お世話になった皆さん、どうもありがとうございました。
リチャード・アーミテージとカート・キャンベルが慶應の三田キャンパスに来ます。10月30日(水)です。事前登録が必要ですが、一般の方も参加できます。次のURLからお申し込みください。
土屋大洋「制御システムのサイバーセキュリティ」『治安フォーラム』2013年11月号、49〜52ページ。
先日、見学させていただく機会のあった宮城県多賀城市の制御システムセキュリティセンターを中心に書きました。
土屋大洋「ビッグデータの威力」『治安フォーラム』2013年10月号、30〜33ページ。
連載の第4回。NHKのクローズアップ現代に出演させてもらったことで刺激を受け、書きました。プリズムについての続きです。
土屋大洋「プリズム問題が明らかにした米外国情報監視法(FISA)の課題」『治安フォーラム』2013年9月号、49〜52ページ。
連載の第3回。すでに第4回(10月号)、第5回(11月号)の原稿を提出済みなので、なんだか時差を感じてしまう。そして、今は第6回(12月号)の原稿を書いている。
土屋大洋「サイバースペースのガバナンス」日本国際問題研究所「グローバル・コモンズ(サイバー空間、宇宙、北極海)における日米同盟の新しい課題 分析レポート」、2013年8月。
まあ、新しいことは書いてないですが、一応。年度末までに倍の長さの報告書にしないといけないそうです。
21世紀政策研究所新書-38「サイバー攻撃の実態と防衛」(2013年4月11日開催)
4月に参加した21世紀政策研究所のシンポジウムの様子が電子ブックになりました。オンラインでもPDFでも読めます。
土屋大洋「日本の新しいサイバーセキュリティ戦略」『治安フォーラム』2013年8月号、48〜51ページ。
連載の第2回です。5月21日に案が公表され、6月10日に最終決定した日本の新しいサイバーセキュリティ戦略について、私から見たときのポイントをまとめています。
土屋大洋「議場の比較研究(2) 権力の館としての米国議会議事堂」慶應義塾大学JSPワーキングペーパー、第6号、2013年7月。
ついでにこんなのも出た。大学院の授業で取り組んできた「権力の館」シリーズ。清水唯一朗さんの日本の国会議事堂のワーキングペーパーも同時公開。
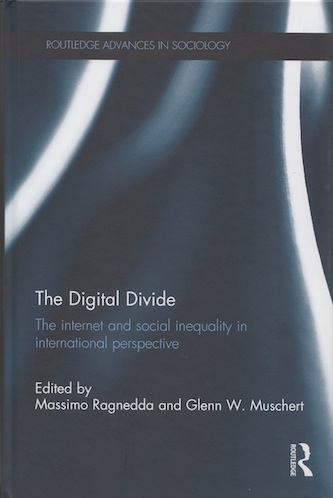
Mito Akiyoshi, Motohiro Tsuchiya and Takako Sano, “Missing in the Midst of Abundance: The Case of Broadband Adoption in Japan,” Massimo Ragnedda and Glenn W. Mushert, eds., The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective, London: Routledge, 2013, pp. 85-103.
専修大学の秋吉美都先生と総務省の佐野貴子さんと行った共同研究が英語の本に収録された。良かった、良かった。もっと英語の成果は増やしていきたい。国際会議で話す機会はずいぶん増えたけど、それだけでは業績にはならない。こうして活字にならないとね。この英語版は、もともとワシントンDCのTPRCでの報告が元になっている。同じ共同研究の日本語の成果はこちら。
土屋大洋「序論 作戦領域の拡大と日本の対応—第四と第五の作戦領域の登場—」『国際安全保障』第41巻1号、2013年6月、1〜11頁。
国際安全保障学会の学会誌で「作戦領域の拡大と日本の対応」という特集が組まれ、その編集主任をさせていただいた。そのうち学会のウェブにも目次が載ると思うが(7月2日現在、載っていない)、加藤朗、橋本靖明、鈴木一人、永岩俊道の各氏にご寄稿をいただいた。私のところは序論だが、他の4本は読み応えがある。
土屋大洋「非伝統的安全保障としてのサイバーセキュリティの課題―サイバースペースにおける領域侵犯の検討―」渡邉昭夫編『防衛戦略研究会議論文集 2010年代の国際政治環境と日本の安全保障―パワー・シフト下における日本』防衛研究所、2013年。
防衛省防衛研究所の研究会で11月に報告したものを、1月末に原稿に書き直したもので、半年以上経ち、古くなってしまった感がある。その間に、マンディアント報告書、韓国への攻撃、米中首脳会談、プリズム問題などがあった。ただ、これを書いていたときも、忙しくなり始めのときで、けっこうつらかった。
ここで書いて領域侵犯の問題は、一昨日(6月28日)、ソウルで行われた会議でも報告した。ところが、やや過激な意見だったらしく、中国からの参加者には受けが良かったが、他の国の人たちは困惑し、司会のハンガリー人は完全に誤解してしまった。「自由なインターネットを守ろう」という意見とは必ずしもそぐわないのだが、防衛省や自衛隊のサイバーセキュリティを考えるときには、どこまでが日本の主権が及ぶ範囲なのかを考えないとどうにもならない。データやトラフィックに基づく境界設定を考えるとぐちゃぐちゃになるが、設備ベースの境界を設定すれば簡単なはずだ。しかし、それはサイバースペースの分断化にもつながりかねない。この最後の点は、必ずしも外交的な方針とはそぐわない。
一つの問題提起としての原稿である。
土屋大洋「プリズム問題で露呈した、オバマ政権下で拡大する通信傍受とクラウドサービスの危うさ」DIAMOND ONLINE(2013年6月17日)。
プリズム問題について歴史的な経緯を書かせていただきました。(いろいろ追われていた時にすぐ書けとのお話だったので、タイトルも小見出しも付けない原稿を出したのですが、うまくまとめてくださいました。)
土屋大洋「米国におけるサイバーサイバーセキュリティ政策」日本国際問題研究所編『米国内政と外交における新展開』(2013年3月)
昨年度の研究会の報告書が公開されています。前半は新しいことは書いていませんが(その点は大変申し訳なく思っています)、後半で議会の対応について書いたのはここが初出です(この原稿にはそこしか見るべきところがありません)。その後、いろいろなところでネタにしています。(これを書いている頃は苦しかった。その後、もっと苦しくなった。とにかく、編集担当の方にご迷惑をおかけしました。すみませんでした。)
21世紀政策研究所「サイバー攻撃の実態と防衛 報告書」(2013年5月)
作成に携わった報告書が完成しました。(苦しいプロジェクトでした。企業のことはよく分からず、他のメンバーの皆さんにたくさん助けていただきました。)
土屋大洋「インターネットとインテリジェンス機関」『治安フォーラム』2013年7月号、38〜41ページ。
「インターネットとインテリジェンス」というタイトルで連載をさせていただくことになりました。その第1回です。