このエントリーは、一部の方には気に障る言い方があるかもしれませんが、ご容赦ください(このブログは検索エンジンになるべく引っかからないようにしているので、さほど読者はいないと思いますけど)。
***
大学院プロジェクトの課題図書なのでクリス・アンダーソンの『ロングテール』を読んでいる。ワイアードの元の論文は読んでいたし、まだロングテール論がそれほど話題になる前にアンダーソンの講演も聴いたことがある。しかし、こうやって一冊の本になって読み直すとやはりおもしろい。
読みながら、別のことを考え始めた。学者に求められていることだ。「ロングテール」というのは分かりやすいキーワードで、コンセプトもシンプルだ。シンプルなコンセプトで多くの事象を切れるところが理論的には優れている。しかし、シンプルであるが故にみんな分かった気になって軽視してしまうところがある。「ああ、またロングテールね」というわけだ。自分でも分かってしまうことを聞かされるとなぜかがっかりする人が多い。アンダーソンは編集者であって学者ではない。しかし、外国の「有名」な人という点では何となく「学者っぽい人」というイメージになっているのではないかと思う(しかし、アンダーソンが何者かということは話の本筋ではない)。
私はこれまで、書くときも話すときも、できるだけ分かりやすくしようと心がけてきた。意味不明の文章では出版しても仕方ないし、聞いている人が理解できない話をしても時間の無駄になるだけだろうと思ってきた。そのためには少々誇張した言い方や、単純化した言い方もしてきた。
しかし、それは学者に求められていることではないということがだんだん分かってきた。というのは、上記のような書き方、言い方をすると腹を立てる人がたまにいるのだ。つい先日、私がしたコメントに対して「ずいぶん乱暴な言い方でつまらない。もっと本質を議論するべきだ」とコメントしたビジネスマンがいた。私が「では本質はどこにあると思うのか」と質問すると、「私より経済学や専門のことが分かっている人が集まっているのだから、もっと議論すべきだ」というのが彼の答えだった(私が経済学者ではないということを知らないのだと思うし、まして私が何を研究しているのかも知らないで彼はコメントしたのだろう)。自分で答えを持っていて批判するのではなく、おそらくは自分が理解できてしまうことを、学者と呼ばれている人が話しているのが気に入らないのだろう。
こういう経験はこれまでも何度となくあった。学者相手だと、議論をシンプルにして原則論で戦おうという雰囲気になるが、学者ではない人は(まだ仮説の段階だが)難しくて高尚な話を聞きたがる。パネル討論の司会を任されたとき、議論を絞ってシンプルなフレームワークを設定したのだが、パネルの最後になってパネリストの企業役員が、物事はそんなに単純じゃないと一言けちを付けて帰っていったことがある。
実業界から学界に移ってきた人は二つのパターンに分かれる。第一に「自分は学者ではない」と開き直って自分の経験してきたことを再生しながらやりすごそうとする人。第二に、やたらと「学者とは」「学問とは」ということにこだわって生きていこうとする人だ。端から見ていてそんなにこだわらなくてもあなたは十分学者ですよといいたくなるほど思い詰めて研究する人もいる。何か自分の知らない学問奥義があるに違いない、それを知りたいと息巻くのだ。
文章についても同じことが言える。難解なものほど読み甲斐があるのだ。解釈の余地が大きいほどおもしろいとされる。私の原稿についていえば、分かりやすく書いてあるものほど評判が悪い(ただ単に私の原稿がおもしろくないというだけなら話は別ですけどね)。自分で読んでも難解なものほど引用されることが多い。「本当に分かっているのかな」と不思議になる。
つまり、私の今のところの作業仮説はこうだ。「人は分かってしまうほど不満になる。理解できないことにこそ知的喜びを見出す。」学者には分からない話をして欲しいのだ。難解な古典が読み継がれているのも同じ理由だ。ほとんどの人が挫折してしまうような難解な本でも、それが古典とされるとすばらしいものに思える。自分が理解しているかどうかは実は関係ない。
そうすると、学者に求められていることとは、物事をシンプルに説明する仮説や理論を提示することではなく、難解な物事をさらに難解に説明する理論を提示することなのかもしれない。難解な議論で煙に巻いてしまう方が学者の行動としては正しいのかもしれない。なるべく分かりやすく、(できればユーモアも交えようと努力しながら)議論しようとしてきた私の努力は、世の中が求めているものと違っていたのかもしれない(ただし、アメリカでは私のやり方はおそらく間違っていない。他の日本人の話が相対的に退屈なせいもあると思うが、シンプルなアイデアで本筋を話した方が活発で有益な議論につながる)。
この仮説を検証してみたい誘惑に少し駆られている。授業ではあまりやらない方がいいような気がするが、これからしばらく、学会パネルの司会、学会発表、ビジネスマンの前での講演などが続く。どうしようかなあ……。
(しかし、私の仮説が正しければ、このエントリー自体も批判を受けることになるはずだ。単純な仮説で説明しようとしているからだ。「バカにするな」とか「それはお前の問題だ」とか、そんな感じかな。まあいいや。)









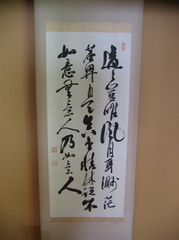



 メディアコムの菅谷先生を中心に続けてきた研究会の成果が出た。私の担当章は、『ブロードバンド時代の制度設計』という本で書いた「セルフ・ガバナンスの意義と変容」のアップデート版になる。
メディアコムの菅谷先生を中心に続けてきた研究会の成果が出た。私の担当章は、『ブロードバンド時代の制度設計』という本で書いた「セルフ・ガバナンスの意義と変容」のアップデート版になる。
 研究会(ゼミ)合宿と採点を終え、ようやく苦しい時期を切り抜けた(写真は帰りに真鶴半島で撮ったもの)。秋学期の採点量は春学期よりはるかに少ないけど、手抜きはできない。卒論の数もこれまでで最も多かった。しかし、自分が学生だった頃は同期のゼミ生が20人以上いたから、先生はもっと大変だったに違いない。
研究会(ゼミ)合宿と採点を終え、ようやく苦しい時期を切り抜けた(写真は帰りに真鶴半島で撮ったもの)。秋学期の採点量は春学期よりはるかに少ないけど、手抜きはできない。卒論の数もこれまでで最も多かった。しかし、自分が学生だった頃は同期のゼミ生が20人以上いたから、先生はもっと大変だったに違いない。
