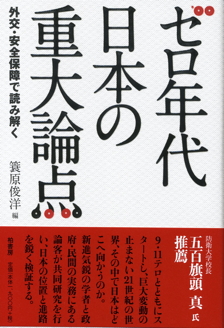大川恵子「SOI-ASIA Project—インターネットによるアジア諸国の高等教育推進プロジェクト—」『海外電気通信』2006年7月号、51〜60ページ。
SFCにいるとSOI(School on the Internet Project)の話はしょっちゅう出てくるんだけど、その仕組みはよく知らなかった。
衛星回線は、周囲のインフラ整備レベルに左右されず、比較的短期間で場所を選ばず回線を構築できるという特徴を有したインフラである。衛星回線を利用することにより、地上線の有無に関わらず、島嶼や山間部でもインターネット環境を構築することができ、学生はどのような地域にいても、広帯域なインターネット環境を利用して授業を受けることが可能となる。
確かに、衛星がすでに打ち上がっていて使えればそれに越したことはない。SOIは衛星を受信のみで使うようにしていて、アジア各国のパートナー校からの発信は128kbps以上の既存のインターネット回線を使うようにしている。例えば、コンテンツをダウンロードしようとするとき、IETFで標準化しているUDLR(UniDirectional Link Routing)を使って、有線でリクエストを出し、衛星経由でコンテンツが落ちてくるようにできる。
しかし、そもそも有線アクセスのない島嶼国ではやはりこのシステムも難しいのだろうか。