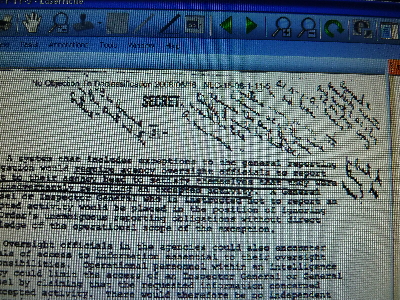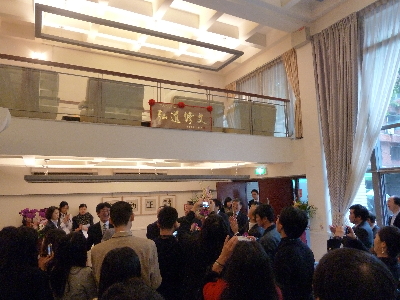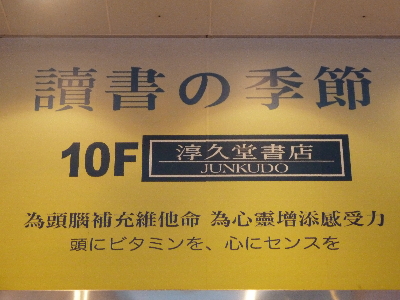チュニジアから始まった動乱が中東諸国に広がっています。ソーシャル・メディアが政治体制に影響を与えることは、すでにいろいろなところで議論されています。クレイ・シャーキーがフォーリン・アフェアーズに「ソーシャル・メディアの政治的パワー」という文章を書いていますし、ヒラリー・クリントン長官が昨年に続き、今年もインターネットの自由に関する演説を行いました。私の『ネットワーク・ヘゲモニー』にも中国の反日デモを題材に書いてあります。
『ネットワーク・ヘゲモニー』にはウィキリークスやフェイスブックのことはほとんど書けなかったのですが、脱稿後にいろいろ読んでみて、一連の動きは「透明性革命」といえるだろうと思い始めました。「透明な革命」ではありません。「社会の透明性を求める革命」という意味です。
デビッド・カークパトリック『フェイスブック 若き天才の野望』(日経BP、2011年)には以下のような言葉があります(290ページ)。
自分が誰であるかを隠すことなく、どの友だちに対しても一貫性をもって行動すれば、健全な社会づくりに貢献できる。もっとオープンで透明な世界では、人々が社会的規範を尊重し、責任ある行動をするようになる。
� だからこそ、フェイスブックCEOのザッカーバーグが実名主義にこだわっているのは納得がいきます。
また、デヴィッド・リー&ルーク・ハーディング『ウィキリークス アサンジの戦争』(講談社、2011年)には、大量の米国の公電をウィキリークスのジュリアン・アサンジに渡したブラッドリー・マニング技術兵の言葉として、以下の引用があります(31ページ)。
情報は自由でなければならない。情報は社会全体のものだ。オープンになれば……公共の利益になるはずだ……人々に真実を知ってほしい……それが誰であっても……情報がなければ、公衆として情報にもとづいた決断など下せないのだから�
「情報は自由でなければならない(information wants to be free)」というスチュアート・ブランドの言葉は誤解されている言葉で、もともと「フリー」は「無料」という意味で使われましたが、ハッカー倫理の一つとして「自由」という意味も与えられるようになりました(http://www.asahi.com/tech/sj/long_n/03.html)。
インターネットでは、一度流れた情報は取り消すことができなくなります。さまざまなところに記録され、残ってしまいます。それはプライバシー侵害などのリスクと背中合わせなのですが、政府や社会の不正と戦おうという人々にとっては、強力なツールとなります。ザッカーバーグやマニング、そしてアサンジといった人たちは、そのことを強く意識しているのでしょう。
そして、そのツールの強さに気づいた人々が中東の国々に現れ、大きなうねりとなっています。私の博士論文(とそれを書き直した出版した『情報とグローバル・ガバナンス』)は、国家と情報の関係を論じ、政府が情報を独占しようとする国があるということを指摘しました。しかし、情報は『ネットワーク・ヘゲモニー』で論じたように、国家や組織や制度が作り出す壁を突き抜けていく力を持っています(この点、後輩の山本達也君が良い引用とレビューをしてくれていますhttp://www.tatsuyayamamoto.com/tyblog/2011/02/post-160.html)。情報通信技術は、壁の向こうにあった秘密を暴き出し、透明性をもたらします。
しかし、この透明性革命が多くの人命を奪っている現実は、受け入れがたいものがあります。そして、情報通信技術が作り出す創発的なデモは、時に大きな力になりますが、権力の空白を埋めることはできません。ザッカーバーグが求めるような「責任ある行動」につなげていく局面が今後必要になるでしょう。それができなければ、混乱が長期化してしまいます。透明性が高まった社会で、責任ある政治ができる指導者が出てくるかどうかが鍵になります。