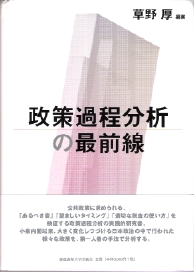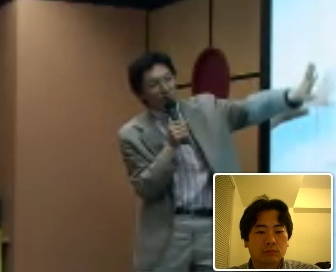MITの先生二人と食事に行った。そのうちの一人が本を出したのでそのお祝いも兼ねている。こちらでは200ページの本は薄いと判断されて業績にならないのだそうだ。どうりで300ページとか400ページとかいう本が多いわけだ。
ひとしきり話をした後、あるテーマについて彼ら二人がすごい勢いで議論を始めてしまい、話についていけなくなる。同僚とでも激しく議論をするのだなあと感心。でももちろん人間関係が悪化するわけではなく、最後はハグをして分かれる。
二人のうち一人と私はジャズ・クラブへ。こちらでは夜遊びなんてしないのだが、良い機会なので連れて行ってもらう。ボストンには有名なバークリー音楽大学があり、その界隈にはジャズ・クラブがたくさんある。今回行ったところは、普通のジャズではなくて、ロックに近い激しいドラムとベースがおもしろかった。タングルウッドのクラシックも良いが、こういうのも楽しい。
音楽の合間に、ある有名な先生のうわさ話を聞く。その先生はライバル大学からかなり良い条件で引き抜きのオファーを受けた。ところが、そのオファーがあったことを人に話してしまうのだ。日本だと人事の話は極秘で進められることがほとんどで、途中で漏れると横やりが入ってダメになることが多い。しかし、こちらではわざと公にして、周囲の反応を見る。案の定、その有名な先生は現在の大学の学長から良い条件で慰留のオファーがあり、残ることになった。へええとこれにも感心してしまう。アメリカの大学の教員は給料で差を付けられるからこんなことも可能なのだろう。日本の大学は年齢給と勤続給で決まることが多いから、インセンティブを付けられない。
夜の12時を過ぎて帰宅することに。帰る途中、「明日は寝坊できるの?」と聞くと、「いや、9時から5時のペースで仕事することにしているんだ」とのこと。もうこちらの大学は夏休みに入っているから、ゆっくりできるはずなのに、3人の子供の面倒を見ながら自宅で毎日同じペースで仕事をしているそうだ。おまけに夜遊びも欠かさない。
せっかくの自由なのだからと最近の私は勝手気ままな生活をしている。好きな時間に研究し、眠くなったらひたすら眠る。何にもしない日もある。日本のある有名な先生に生活のリズムを聞いたとき、「リズムは一定してない。好きなときにやるだけだよ」と言っていた。その先生は自宅近くに仕事場を持っていて、そこにベッドもあるので、本当に好きなようにやっているようだった。高齢なのでそんなに睡眠時間が必要ではないらしいし、引退して授業も持っていないからそれで構わないらしい。
そのまねをすべく、好きなようにやっていたのだが、どうも私には合わない。不規則な生活をしていると集中力が持続しないような気がする。調子に乗って徹夜などすると、その後の二、三日は影響が出てしまう。結局のところ、集中できる時間を最大限確保するためには規則正しく、ルーティーンで研究をするほうが良いのかもしれない。ムラのある仕事をするよりも、たぶん毎日少しずつ積み重ねていく方が結果が出るのだろう。