モバイル時代の英語力強化法
人工知能学会誌 Vol. 25 No. 5(2010 年9 月)の「世界のAI,日本のAI」のコーナーにエッセイを書きました。
井庭 崇, 「モバイル時代の英語力強化法 ―日本にいながらの環境構築―」, 人工知能学会誌 Vol. 25 No. 5, pp.710-714, 2010 年9 月
以下、そのイントロ部分。
昨年度(2009 年度),1 年間大学業務をお休みし,海外で研究する貴重な機会をいただいた.筆者が所属したのは,MIT Center for Collective Intelligence という,マサチューセッツ工科大学スローン経営学大学院の研究所である.研究所のディレクターは,『The Future of Work』[Malone 04] の著者であり,情報技術が経営・組織をどう変えるのかを長年論じてきたThomas W. Malone 教授である.オープンソース開発やオープンコラボレーション,予測市場などの「集合知による新しい組織化」が社会・組織の在り方をいかに変えるのかを考え,実践する研究所である.
筆者は, この研究所のResearch Scientist であるPeter Gloor 氏と,彼のもとに集まる学生・研究員との共同研究プロジェクトに参加した.Gloor 氏は,ダイナミックなネットワーク分析によってトレンドの予測をするという,この分野では珍しいタイプの研究をしている研究者である(その成果は,彼の『Swarm Creativity』[Gloor 06] や『Coolhunting』[Gloor 07],『Coolfarming』[Gloor 10] という本で紹介されている).筆者は,この研究所を軸足として,MIT Media Lab,Harvard University Graduate School of Design,Harvard Kennedy School,Northeastern University などにも,ことあるごとに足を運んだ.ボストンならではの多様な知的コミュニティとそこでの交流を垣間見ることができた.
このエッセイでは,筆者自身が1 年間の滞在を通じて最も強く感じ考えたことについて書こうと思う.それは,簡単にいうならば,「英語力は,いったいどうやったら伸ばすことができるのか」ということである.筆者は滞在中,これまで日本で長い期間英語教育を受けてきたにもかかわらず,どうして自分はこれほどまでに英語ができないのか,と何度も情けなるとともに,自分や日本の英語教育に対してある種の怒りさえ覚えた.日米の研究スタイルの違いなどよりも,何よりもこの英語の問題が最も痛感した問題なので,このエッセイのテーマを「英語」にすべきだと判断した.変に格好をつけたりせず,まずは,筆者の経験を赤裸々に語ることにしよう.そのうえで,どうしたら英語力を高めることができるのか,特に日本にいながらそれを行うにはどうしたらよいのかについて,筆者の考えを書くことにしたい.
・・・
続きは、学会誌の方をご覧ください。かなり具体的な方法や、おすすめのコンテンツについても書いてあります。以下が、エッセイ内の目次です。
以下、そのイントロ部分。
昨年度(2009 年度),1 年間大学業務をお休みし,海外で研究する貴重な機会をいただいた.筆者が所属したのは,MIT Center for Collective Intelligence という,マサチューセッツ工科大学スローン経営学大学院の研究所である.研究所のディレクターは,『The Future of Work』[Malone 04] の著者であり,情報技術が経営・組織をどう変えるのかを長年論じてきたThomas W. Malone 教授である.オープンソース開発やオープンコラボレーション,予測市場などの「集合知による新しい組織化」が社会・組織の在り方をいかに変えるのかを考え,実践する研究所である.
筆者は, この研究所のResearch Scientist であるPeter Gloor 氏と,彼のもとに集まる学生・研究員との共同研究プロジェクトに参加した.Gloor 氏は,ダイナミックなネットワーク分析によってトレンドの予測をするという,この分野では珍しいタイプの研究をしている研究者である(その成果は,彼の『Swarm Creativity』[Gloor 06] や『Coolhunting』[Gloor 07],『Coolfarming』[Gloor 10] という本で紹介されている).筆者は,この研究所を軸足として,MIT Media Lab,Harvard University Graduate School of Design,Harvard Kennedy School,Northeastern University などにも,ことあるごとに足を運んだ.ボストンならではの多様な知的コミュニティとそこでの交流を垣間見ることができた.
このエッセイでは,筆者自身が1 年間の滞在を通じて最も強く感じ考えたことについて書こうと思う.それは,簡単にいうならば,「英語力は,いったいどうやったら伸ばすことができるのか」ということである.筆者は滞在中,これまで日本で長い期間英語教育を受けてきたにもかかわらず,どうして自分はこれほどまでに英語ができないのか,と何度も情けなるとともに,自分や日本の英語教育に対してある種の怒りさえ覚えた.日米の研究スタイルの違いなどよりも,何よりもこの英語の問題が最も痛感した問題なので,このエッセイのテーマを「英語」にすべきだと判断した.変に格好をつけたりせず,まずは,筆者の経験を赤裸々に語ることにしよう.そのうえで,どうしたら英語力を高めることができるのか,特に日本にいながらそれを行うにはどうしたらよいのかについて,筆者の考えを書くことにしたい.
・・・
続きは、学会誌の方をご覧ください。かなり具体的な方法や、おすすめのコンテンツについても書いてあります。以下が、エッセイ内の目次です。
「モバイル時代の英語力強化法 ―日本にいながらの環境構築―」(井庭 崇)
1. 米国での研究生活で感じた自分の英語力の低さ
1.1 スピーキング
1.2 リスニング
1.3 ライティング
1.4 リーディング
2. 日本にいながら英語力を高める方法
2.1 「言語のシャワー」を浴びる環境をつくる
2.2 表現のストックをため込む/使う
3. 多面的なアプローチによるスパイラルアップ
英語漬け生活 | - | -

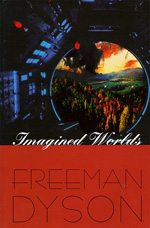
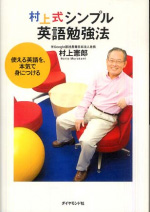 『村上式シンプル英語勉強法:使える英語を、本気で身につける』
『村上式シンプル英語勉強法:使える英語を、本気で身につける』