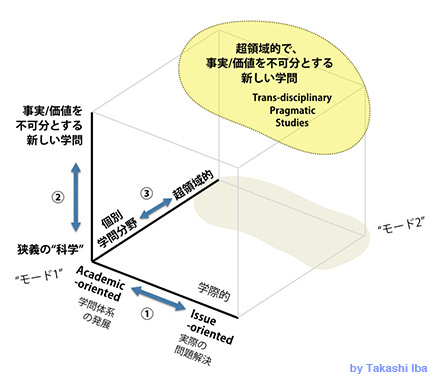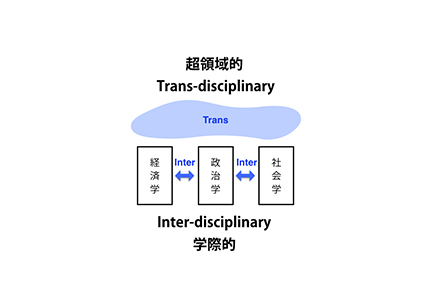哲学するということ:永井均『西田幾多郎』を読んで
哲学者 永井 均さんの『西田幾多郎:<絶対無>とは何か』なかで、哲学するということはどういうことか、ということについてのとても面白い発見的な部分があった。
この本の冒頭で、この本の位置付けについて書いている部分に、次のように書かれていた。面白い。
これは、自分がこれから考え書くときの参考にとてもなる。これまでわかっていることをベースに積み上げていく自然科学的な学問をかじったあとに、社会学や哲学にくると、つい、「誰々がこう言っている。ゆえに、そこから考えると、こう言える」ということで、自分の論を展開しがちになる。しかし、自然科学の場合と異なり、そのベースになっているものは、ある先行者のひとつの考えや見方にすぎないので、それを踏まえても、正しいとは限らない。僕が社会学的な研究を始めたときに学んだのはそのことだった。だからといって、先行研究を一切踏まえなくていいわけではない。
必要なのは、先人たちが「どのように考えたのか、それはなぜなのか」を踏まえ、自分が考える際の一つの仮設(仮説ではなく仮に設置する補助具)として用いるということだ。つまり、結論だけを利用・応用するのではなく、自分も同じように深く考えることが求められるのである。先行者が歩んだ同じ道を歩くときには、当然、その人と同じように内側から見て考えることになるので、結論としては、似たようなことになる。そのまま歩みを進めて、自分の考えたいことを考えてみる。そういう試みである。
その意味で、哲学では、そこで得られた結論ではなく、問いや視点、考え方を学ぶことが重要になる。
そのことを端的に見事に言葉にしてくれている文章に、僕は、ここで初めて出会ったように思う。「私は西田よりもうまくそれを言い当てている、という可能性はもちろある」という感覚は、僕も、ルーマンやアレグザンダーに対して感じたことがある。僕の場合は、ルーマンは、社会システム理論を社会学として読んだときではなく、創造システム理論をつくるときに、パレフレーズしながら読んだときが、ルーマンの問いや視点、考え方をなぞることで、最もルーマンを理解できたと感じた。アレグザンダーについても、建築ではなく行為のパターン・ランゲージとは何かということを考えたときや、無我の創造について考えるなかで、アレグザンダーの視点や彼の歩んだ道を辿り直す(しかし、別のことを発想するために)ということになり、もっともアレグザンダーを内側から理解し、彼よりもうまく説明できるのではないかという感覚をもった。
実際にそうできているかは別問題だが、ここで永井さんが言わんとしていることは、きわめて重要だ。つまり、自分が追い求めている問題について、哲学するために、先人の哲学の道をくぐり直す。それこそが重要なのだ。創造的読書(クリエイティブ・リーディング)の極みだと言えるだろう。
今後も、自分のなかで「誰々が言っているから・・・(正しい)」という安易な引用を避け、自らが哲学するために、読んでいきたい。そういう意味で、目が覚めるような素晴らしい文章だった。
それでは、自分が追い求めている問題というのはどういうものだろうか。別の箇所の脚注で、とても重要な視点を見つけた。哲学の天才とはどういうものか、ということを書いているが、これは、すなわち、哲学するとはどういうことか、ということである。
僕が、哲学の本を読むとき、多くの場合、あまり楽しめないのは、まさに、この点に関係していると思った。哲学者たちが問題としている論点にあまり興味が湧かないのである。実のところ、永井さんの<私>の問題についても、永井さんにとってかなり重要であることはよく理解できるが、僕自身はその問題に惹かれない。だから、ほとんどついていけなくて理解できない。そういうものなのだろう。
そう考えると、僕は何に(他の人よりも)こだわり続けているのだろうか。それが研究の根本的なテーマであろう。
いま思うのは、僕が、ずっと興味をもっているのは、「新しい発想はいかに生まれるのか」「創造的であることはいかにして可能か」「生きているとはどういうことか」ということである。これは、高校生のときに、オセロ・ゲームのプログラミングをしたときに、どうしたら、対戦相手の人工知能が強くなるのかを考えたときや、詩を自動生成するコンピュータ・プログラムをつくったとき、チャットで会話できるボット(コンピュータ上の人工知能)をつくったとき、そして、コンピュータ・シミュレーション上で人工生命をつくったときや社会シミュレーションをつくったときに原点がある。どれだけ仕込んでも、「なんだ、ぜんぜん賢くならないな」「結局、これを面白いと楽しめる人間の方がすごいな」「シミュレーション上だと新しい進化も、イノベーションも、当然、起きないんだな」ということなどを実感したからだ。
それでは、一体、新しい発想はいかに生まれるのだろうか?創造的であることはいかにして可能なのだろうか?生きているとはどういうことなのだろうか? これが僕の学問的探究の根本にある(ニューラルネットワークの研究をしていた僕は、「それは脳がすごいから」という説明ももの足りないと思い、そこでどういうことが起きると創造的になるのかの原理の方が知りたくなった)。
その点に執拗なまでに興味をもち、そのことのまわりで手を変え品を変え、取り組んでいる。そういうことなのだ。
永井さんのこの箇所を読んで、今後、僕がどういう道に進むべきなのかも、非常にクリアになったと思う。他の人は当たり前に理解し、特段それほど注意を払わないことで、僕が異常に気になってしまうこと、そのことに専念して進んでいくのがよいのだろう。
そういうテーマに触れるときだけ、哲学できるのだろう。先人たちの辿った道も、結果だけ利用させてもらおうという意識ではなく、もう一度追体験するようなかたちで内側から理解し、活かす。その感覚を大切にしながら、これからも研究していきたい。
『西田幾多郎:<絶対無>とは何か』(永井 均, NHK出版, 2006)
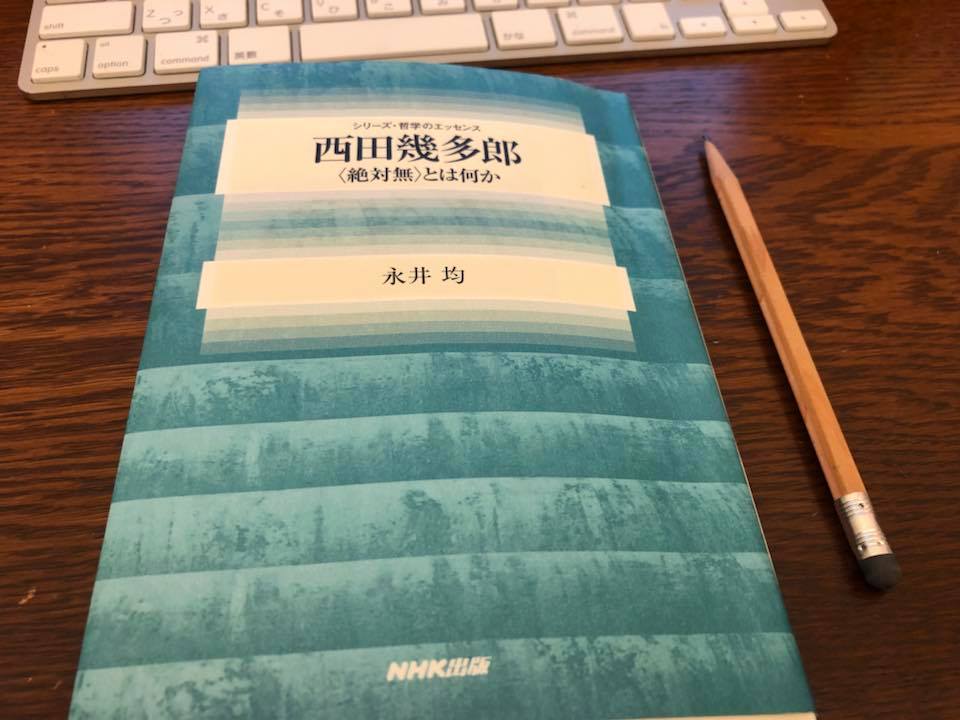
この本の冒頭で、この本の位置付けについて書いている部分に、次のように書かれていた。面白い。
「解説書や入門書に意味があるのは、それがそこで独立に哲学をしている場合だけだと思う。それ以外の仕方で、哲学を伝えることはできないからである。独立に哲学をしているのだから---驚かれるかもしれないが---本書の内容は、実は西田幾多郎とは関係がない。正確にいえば、関係なくてもぜんぜんかまわない。いや、ものすごく関係がある、それどころか西田が言わんとしたことは本書で私が言ったようなことで、私は西田よりもうまくそれを言い当てている、という可能性はもちろある。いや、少なくとも私には西田がそう読めるし、そう読まないとさっぱり意味がわからない。しかし、ほんとうにそうであるかは、私にとってはじつはどうでもいい。西田幾多郎の実態がどうであれ、本書にはそれとは独立の哲学的意義がある。ここで述べられていることは、西田幾多郎という人物を離れて、名なしで剥き出しの哲学的議論として提示されても、それ自体で意味があると思う。それが、独立に哲学をしているということの意味である。
独立に哲学をするなら西田はいらないのではないかと言われるなら、それはちがう。他人の哲学の解説がそれを使って自分の哲学をすることによってしかできないように、自分の哲学のほうも他人の哲学の力で引っ張ってもらわないと進めないという面があるからだ。私はこれまでウィトゲンシュタインとニーチェについても、解説書のようなものを書いたことがあるが、どちらの場合も、彼らに引っ張ってもらいながら、その勢いをかりて自分の哲学を勝手に進めさせてもらった。そして、そういう点で、西田幾多郎の「場所の哲学」は、彼らの哲学に劣らず、素晴らしいものなのである。」(p.7-8)
これは、自分がこれから考え書くときの参考にとてもなる。これまでわかっていることをベースに積み上げていく自然科学的な学問をかじったあとに、社会学や哲学にくると、つい、「誰々がこう言っている。ゆえに、そこから考えると、こう言える」ということで、自分の論を展開しがちになる。しかし、自然科学の場合と異なり、そのベースになっているものは、ある先行者のひとつの考えや見方にすぎないので、それを踏まえても、正しいとは限らない。僕が社会学的な研究を始めたときに学んだのはそのことだった。だからといって、先行研究を一切踏まえなくていいわけではない。
必要なのは、先人たちが「どのように考えたのか、それはなぜなのか」を踏まえ、自分が考える際の一つの仮設(仮説ではなく仮に設置する補助具)として用いるということだ。つまり、結論だけを利用・応用するのではなく、自分も同じように深く考えることが求められるのである。先行者が歩んだ同じ道を歩くときには、当然、その人と同じように内側から見て考えることになるので、結論としては、似たようなことになる。そのまま歩みを進めて、自分の考えたいことを考えてみる。そういう試みである。
その意味で、哲学では、そこで得られた結論ではなく、問いや視点、考え方を学ぶことが重要になる。
そのことを端的に見事に言葉にしてくれている文章に、僕は、ここで初めて出会ったように思う。「私は西田よりもうまくそれを言い当てている、という可能性はもちろある」という感覚は、僕も、ルーマンやアレグザンダーに対して感じたことがある。僕の場合は、ルーマンは、社会システム理論を社会学として読んだときではなく、創造システム理論をつくるときに、パレフレーズしながら読んだときが、ルーマンの問いや視点、考え方をなぞることで、最もルーマンを理解できたと感じた。アレグザンダーについても、建築ではなく行為のパターン・ランゲージとは何かということを考えたときや、無我の創造について考えるなかで、アレグザンダーの視点や彼の歩んだ道を辿り直す(しかし、別のことを発想するために)ということになり、もっともアレグザンダーを内側から理解し、彼よりもうまく説明できるのではないかという感覚をもった。
実際にそうできているかは別問題だが、ここで永井さんが言わんとしていることは、きわめて重要だ。つまり、自分が追い求めている問題について、哲学するために、先人の哲学の道をくぐり直す。それこそが重要なのだ。創造的読書(クリエイティブ・リーディング)の極みだと言えるだろう。
今後も、自分のなかで「誰々が言っているから・・・(正しい)」という安易な引用を避け、自らが哲学するために、読んでいきたい。そういう意味で、目が覚めるような素晴らしい文章だった。
それでは、自分が追い求めている問題というのはどういうものだろうか。別の箇所の脚注で、とても重要な視点を見つけた。哲学の天才とはどういうものか、ということを書いているが、これは、すなわち、哲学するとはどういうことか、ということである。
「実は、哲学は科学と違って非民主的な営みで、凡人は天才の並外れた技芸の前にただひれ伏すしかないという一面がある。ここで天才とは、並外れて頭がいいというようなことではなく、むしろ逆に、普通の人が即座に(あるいは最初から)分かってしまうことがなぜかどうしても分からず、しかも信じがたいほどあきらめが悪く、執拗にその理路を問い続ける一種の化け物のことである。・・・こう規定するなら、西田幾多郎が大天才(超弩級の哲学的な化け物)であったことは疑う余地がない。」(p.69)
僕が、哲学の本を読むとき、多くの場合、あまり楽しめないのは、まさに、この点に関係していると思った。哲学者たちが問題としている論点にあまり興味が湧かないのである。実のところ、永井さんの<私>の問題についても、永井さんにとってかなり重要であることはよく理解できるが、僕自身はその問題に惹かれない。だから、ほとんどついていけなくて理解できない。そういうものなのだろう。
そう考えると、僕は何に(他の人よりも)こだわり続けているのだろうか。それが研究の根本的なテーマであろう。
いま思うのは、僕が、ずっと興味をもっているのは、「新しい発想はいかに生まれるのか」「創造的であることはいかにして可能か」「生きているとはどういうことか」ということである。これは、高校生のときに、オセロ・ゲームのプログラミングをしたときに、どうしたら、対戦相手の人工知能が強くなるのかを考えたときや、詩を自動生成するコンピュータ・プログラムをつくったとき、チャットで会話できるボット(コンピュータ上の人工知能)をつくったとき、そして、コンピュータ・シミュレーション上で人工生命をつくったときや社会シミュレーションをつくったときに原点がある。どれだけ仕込んでも、「なんだ、ぜんぜん賢くならないな」「結局、これを面白いと楽しめる人間の方がすごいな」「シミュレーション上だと新しい進化も、イノベーションも、当然、起きないんだな」ということなどを実感したからだ。
それでは、一体、新しい発想はいかに生まれるのだろうか?創造的であることはいかにして可能なのだろうか?生きているとはどういうことなのだろうか? これが僕の学問的探究の根本にある(ニューラルネットワークの研究をしていた僕は、「それは脳がすごいから」という説明ももの足りないと思い、そこでどういうことが起きると創造的になるのかの原理の方が知りたくなった)。
その点に執拗なまでに興味をもち、そのことのまわりで手を変え品を変え、取り組んでいる。そういうことなのだ。
永井さんのこの箇所を読んで、今後、僕がどういう道に進むべきなのかも、非常にクリアになったと思う。他の人は当たり前に理解し、特段それほど注意を払わないことで、僕が異常に気になってしまうこと、そのことに専念して進んでいくのがよいのだろう。
そういうテーマに触れるときだけ、哲学できるのだろう。先人たちの辿った道も、結果だけ利用させてもらおうという意識ではなく、もう一度追体験するようなかたちで内側から理解し、活かす。その感覚を大切にしながら、これからも研究していきたい。
『西田幾多郎:<絶対無>とは何か』(永井 均, NHK出版, 2006)
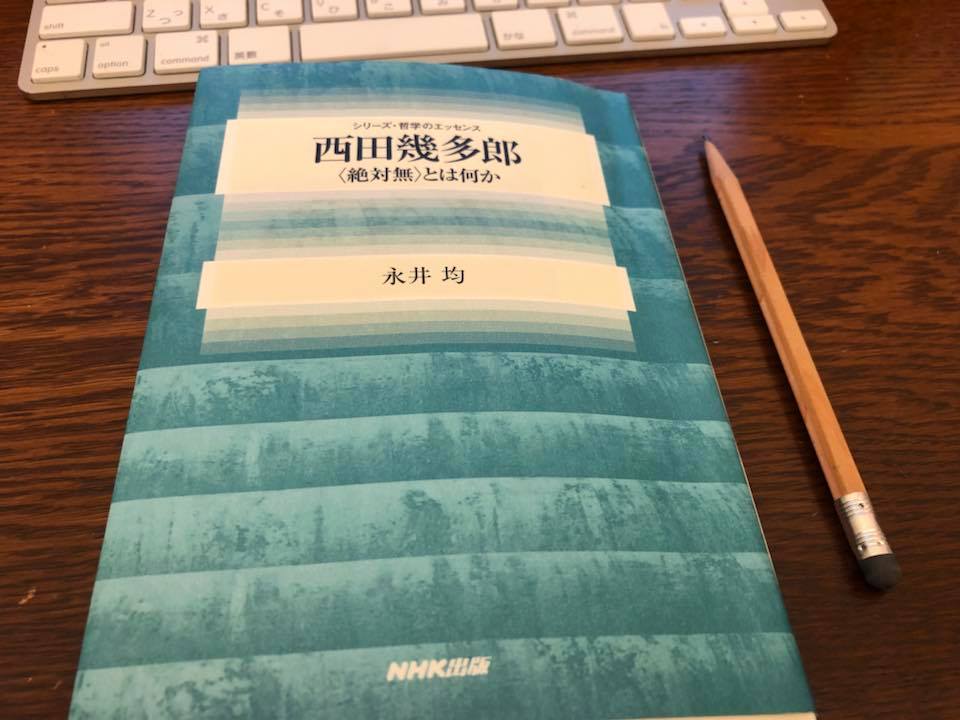
「研究」と「学び」について | - | -