「島」を買いました!
先月、大きな買い物をした。プライベートな「島」を買ったのだ。65平方Kmという、なかなか広い土地。地価が高いので少し迷ったが、思い切って購入してみた。
この「島」というのは、実は、セカンドライフ上に存在するヴァーチャルな島のこと。セカンドライフでは、島を購入するとそこに建物を建てたり、モノを作ったりすることができるようになる。他の人に権限を与えて、一緒に何かをつくりあげることもできる。この新しい世界で、みんなで遊んでみよう!――― そう思って、セカンドライフの島を購入したのだ。
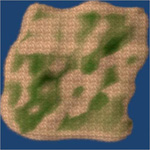 このヴァーチャルな島は、現実世界のお金を支払って購入する。値段は米ドルで$1,675、日本円に換算すると約20万円だ。これが購入の初期費用で、あとは月々$295、つまり約3万5千円を支払うことになる。正直、結構高い。それでも、僕はこの島の購入に踏み切った。というのは、僕の研究会や授業の学生たちに、「新しい遊び場」を提供したかったからだ。そう思うのには、十数年前の僕の経験が関係している。
このヴァーチャルな島は、現実世界のお金を支払って購入する。値段は米ドルで$1,675、日本円に換算すると約20万円だ。これが購入の初期費用で、あとは月々$295、つまり約3万5千円を支払うことになる。正直、結構高い。それでも、僕はこの島の購入に踏み切った。というのは、僕の研究会や授業の学生たちに、「新しい遊び場」を提供したかったからだ。そう思うのには、十数年前の僕の経験が関係している。
僕はちょうどWorld Wide Web (WWW)の黎明期に、大学時代を過ごした。大学2年のとき(1994年)、Mosaicが登場し、目の前にWWWという未開のフロンティアが広がっていることを知った。まだほとんど何も存在しないその世界で、僕はいろいろなものをつくっては公開していった。例えば、オリジナルの絵本やゲーム、ちょっと実用的なシステムなどだ。そうすると、僕の知らない人たちがたくさん僕のサイトに訪れて、楽しんでいった。感想もたくさんもらった。そして、雑誌にもたびたび紹介された。WWW上にはまだ日本発のコンテンツがほとんどない時代だったから、何をやっても珍しく新しかった。こうやって大学時代の僕は、その「新しい遊び場」で考えて、作って、コミュニケートした。この経験が、今の僕をつくっているといっても過言ではない。
こういう経験を、僕の後輩たちにも味あわせてあげたい。そう思ってからもう何年も経つのだが、今回セカンドライフに出会ったとき、これだ!と思った。理屈ではなく、直感的に。僕は大学(SFC)が用意してくれたインターネットを使って、たくさん遊ばせてもらった。今度は僕が、学生のみんなのために場を提供しよう。そう思ったのが、今回セカンドライフに島を買った理由なのだ。
購入後1週間ほどで、更地の島が手渡される。ほんとに何もない土地。ここに何でも自由に構築できる。
何でも自由に―――こういうとき僕はいつも、アラン・ケイの言葉を思い出す。
そういえば、セカンドライフのキャッチコピーも、「Your World. Your Imagination.」だったね。まさに。
* Alan Kay (1977): "Microelectronics and the Personal Computer", Scientific American, September 1977, pp.231-244 (アラン・ケイ, 「マイクロエレクトロニクスとパーソナル・コンピュータ」, 『アラン・ケイ』, アスキー出版局, 1992, p.61-91)
この「島」というのは、実は、セカンドライフ上に存在するヴァーチャルな島のこと。セカンドライフでは、島を購入するとそこに建物を建てたり、モノを作ったりすることができるようになる。他の人に権限を与えて、一緒に何かをつくりあげることもできる。この新しい世界で、みんなで遊んでみよう!――― そう思って、セカンドライフの島を購入したのだ。
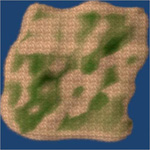 このヴァーチャルな島は、現実世界のお金を支払って購入する。値段は米ドルで$1,675、日本円に換算すると約20万円だ。これが購入の初期費用で、あとは月々$295、つまり約3万5千円を支払うことになる。正直、結構高い。それでも、僕はこの島の購入に踏み切った。というのは、僕の研究会や授業の学生たちに、「新しい遊び場」を提供したかったからだ。そう思うのには、十数年前の僕の経験が関係している。
このヴァーチャルな島は、現実世界のお金を支払って購入する。値段は米ドルで$1,675、日本円に換算すると約20万円だ。これが購入の初期費用で、あとは月々$295、つまり約3万5千円を支払うことになる。正直、結構高い。それでも、僕はこの島の購入に踏み切った。というのは、僕の研究会や授業の学生たちに、「新しい遊び場」を提供したかったからだ。そう思うのには、十数年前の僕の経験が関係している。僕はちょうどWorld Wide Web (WWW)の黎明期に、大学時代を過ごした。大学2年のとき(1994年)、Mosaicが登場し、目の前にWWWという未開のフロンティアが広がっていることを知った。まだほとんど何も存在しないその世界で、僕はいろいろなものをつくっては公開していった。例えば、オリジナルの絵本やゲーム、ちょっと実用的なシステムなどだ。そうすると、僕の知らない人たちがたくさん僕のサイトに訪れて、楽しんでいった。感想もたくさんもらった。そして、雑誌にもたびたび紹介された。WWW上にはまだ日本発のコンテンツがほとんどない時代だったから、何をやっても珍しく新しかった。こうやって大学時代の僕は、その「新しい遊び場」で考えて、作って、コミュニケートした。この経験が、今の僕をつくっているといっても過言ではない。
こういう経験を、僕の後輩たちにも味あわせてあげたい。そう思ってからもう何年も経つのだが、今回セカンドライフに出会ったとき、これだ!と思った。理屈ではなく、直感的に。僕は大学(SFC)が用意してくれたインターネットを使って、たくさん遊ばせてもらった。今度は僕が、学生のみんなのために場を提供しよう。そう思ったのが、今回セカンドライフに島を買った理由なのだ。

購入後1週間ほどで、更地の島が手渡される。ほんとに何もない土地。ここに何でも自由に構築できる。
何でも自由に―――こういうとき僕はいつも、アラン・ケイの言葉を思い出す。
「コンピュータに実行可能なシミュレーションを制約するのは、人間の想像力の限界だけである。」(Alan Kay, 1977)
そういえば、セカンドライフのキャッチコピーも、「Your World. Your Imagination.」だったね。まさに。
* Alan Kay (1977): "Microelectronics and the Personal Computer", Scientific American, September 1977, pp.231-244 (アラン・ケイ, 「マイクロエレクトロニクスとパーソナル・コンピュータ」, 『アラン・ケイ』, アスキー出版局, 1992, p.61-91)
ヴァーチャル世界の探険 | - | -
 この本は、3次元ヴァーチャル世界「セカンドライフ」とは何かを知りたいという人に、僕がいつもおすすめしているものだ。この本には、セカンドライフとはどのようなもので、これまでにどのような企業が参入しているのかなどが、わかりやすくまとめられている。日産やインテル、シェラトンなど初期の参入企業がどのような工夫でその世界をつくりあげたのか、というエピソードはなかなか興味深い。セカンドライフに関する本というと、たいていはカラー画像が多用されていてゲーム攻略本のような雰囲気のものが多いが、この本は縦書きの文章のところどころに白黒の画像が入っているという、いわゆる新書版の本なので、落ち着いて読むことができる。
この本は、3次元ヴァーチャル世界「セカンドライフ」とは何かを知りたいという人に、僕がいつもおすすめしているものだ。この本には、セカンドライフとはどのようなもので、これまでにどのような企業が参入しているのかなどが、わかりやすくまとめられている。日産やインテル、シェラトンなど初期の参入企業がどのような工夫でその世界をつくりあげたのか、というエピソードはなかなか興味深い。セカンドライフに関する本というと、たいていはカラー画像が多用されていてゲーム攻略本のような雰囲気のものが多いが、この本は縦書きの文章のところどころに白黒の画像が入っているという、いわゆる新書版の本なので、落ち着いて読むことができる。 「Second Life」(セカンドライフ)という言葉を聞いたことがあるだろうか。Second Lifeとは、米国リンデンラボ社が提供する3Dヴァーチャル世界のこと。そのヴァーチャル世界では、ユーザーは自分で好きなように「生活」することができる。この世界では、いわゆるオンラインRPG (Role Playing Game)とは違って、敵を倒したり目的を達成するというようなゲーム設定は存在しない。いうなれば、ただヴァーチャルな場が提供されているにすぎない。しかし、海外ではかなりのユーザーが参加していて、いろいろ面白いことが起こっている。そして、日本でも徐々に話題になり始めたところだ。
「Second Life」(セカンドライフ)という言葉を聞いたことがあるだろうか。Second Lifeとは、米国リンデンラボ社が提供する3Dヴァーチャル世界のこと。そのヴァーチャル世界では、ユーザーは自分で好きなように「生活」することができる。この世界では、いわゆるオンラインRPG (Role Playing Game)とは違って、敵を倒したり目的を達成するというようなゲーム設定は存在しない。いうなれば、ただヴァーチャルな場が提供されているにすぎない。しかし、海外ではかなりのユーザーが参加していて、いろいろ面白いことが起こっている。そして、日本でも徐々に話題になり始めたところだ。 興味深いのは、Second Lifeを提供しているリンデンラボ社はその世界にほとんど何もつくっていないということ。彼らが提供しているのは、基本的には何もない土地だ。そこに魅力的な建物を作っているのは、ユーザーたち(企業も含む)なのだ。それはとてもWeb2.0的な出来事だといえるだろう。
興味深いのは、Second Lifeを提供しているリンデンラボ社はその世界にほとんど何もつくっていないということ。彼らが提供しているのは、基本的には何もない土地だ。そこに魅力的な建物を作っているのは、ユーザーたち(企業も含む)なのだ。それはとてもWeb2.0的な出来事だといえるだろう。 そもそも、目的のない仮想世界なんて、そんなに面白いのかな? と初めは思うかもしれないけれど、意外とハマる、というのが僕の実感。いろいろな場所を旅しながら写真を撮っておくことができるのだけど、それが現実世界での経験と同様に、とても思い出深い写真に思えてくるのが、なんとも不思議だ。自分でモノをつくったりすると、世界に対する愛着はますます強まる。
そもそも、目的のない仮想世界なんて、そんなに面白いのかな? と初めは思うかもしれないけれど、意外とハマる、というのが僕の実感。いろいろな場所を旅しながら写真を撮っておくことができるのだけど、それが現実世界での経験と同様に、とても思い出深い写真に思えてくるのが、なんとも不思議だ。自分でモノをつくったりすると、世界に対する愛着はますます強まる。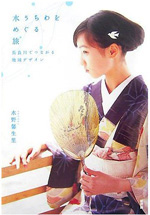 この本を手にすると、まず素敵な装丁に魅せられてしまう。とてもみずみずしく、さわやかなのだ。
この本を手にすると、まず素敵な装丁に魅せられてしまう。とてもみずみずしく、さわやかなのだ。