『社会を越える社会学』(ジョン・アーリ)

ジョン・アーリ, 『社会を越える社会学:移動・環境・シチズンシップ』
この本では、「移動」(モビリティ)という観点から、グローバリゼーション時代における新しい社会学のパラダイムの提唱が試みられている。特に「国民国家」内における「社会」を主な研究対象としていた従来の社会学に対し、より流動的で移動がベースとなった捉え方をしていこうという。その意味で、(国民国家内における)「社会」を越える社会学、というわけだ。
「本書のねらいは、二十一世紀における一つの「学問分野」としての社会学に必要とされる研究カテゴリーを発展させることにある。本書は、ヒト、モノ、イメージ、情報、廃棄物の多種多様な移動について検討し、これらの移動相互の複雑な依存関係や、その社会的な帰結を研究対象にする〔新たな〕社会学の宣言をおこなう。」(p.1)
「再構成された社会学の中心には、社会(ソサエティ)よりも移動(モビリティ)を据えるべきだ」(p.368)
この本で、まず面白かったのが、「場所」についての次の指摘だ。
「「場所」という単一の範疇は、すでに確立しているというよりはむしろ、主催者、ゲスト、建物、モノ、機械が特定の時刻に特定の場所で何らかのパフォーマンスをおこなうためにたまたま寄り集まるというような複雑なネットワークのなかで、その意味が示されることになる。そして場所はパーフォマンスのシステム、すなわち、他の諸組織や建物、モノや機械とのネットワーク化されたむすびつきを通して現実のものとなり、しかも意図せざる結果として安定的なものとなるようなシステムを介して(再)生産される。それゆえ、場所はダイナミックなもの――「動きの場」であり、ひんぱんに移動し、必ずしも一箇所に停泊しない船のようなもの――である。「新しい移動」パラダイムでは、場所それじたいが人間、非人間の行為主体からなるネットワークの内部で、遅いか早いか、遠距離か近距離かの違いはあれ、旅するものと考えられている。場所は関係のようなものであり、人、物材、イメージ、そしてそれらがおりなす差異のシステムの布置構成のようなものである。」(p.xiv)
場所について考えるとき、まず物理的な場所についてイメージしがちであるが、ここで論じられているのは、社会的な関係性における「場所」である。物理的存在としての固定的な「場所」と、関係性のなかでの浮遊し、ゆらぐ「場所」 ――― 場所について考えるときには、この二重性について考えることが重要だと思う(この場所のもつ二重性については考えていることがあるので、それについてはまた今度書きたいと思う)。この二重性は、やはり「粒子」と「波」の性質を併せ持つ量子の話を思い起こさせる。
興味深いのは、アーリ自身もこの本のなかで、移動パラダイムの社会学に関係するものとして、量子力学的な考え方を取り上げていることだ。以下のように、Zoharらの『The Quantum Society: Mind, Physics and a New Social Vision』
「ゾーハーとマーシャルが『量子的社会』という観念を練り上げている。絶対時間、絶対空間という固定したカテゴリー、相互作用する「ビリヤードの球」からなる剛体の不可入性、そして完全に決定論的な運動法則に基づく古典物理学に見られる、かつての確実性の世界が崩壊したとゾーハーらは述べる。それに代わるのが、「量子物理学の奇妙な世界、つまり空間、時間、物質の境界をものともしない奇怪な法則からなる不確定な世界」である(Zohar and Marshall 1994: 33)。さらにはゾーハーらは、波動/粒子の作用と社会生活の創発的性格との類似性を見いだしている。「量子的実在は……潜在的には、粒子のようでもあり波動のようでもある。粒子は単一体であり、空間的、時間的に定位され計測可能なもので、ある時点でどこかに存在する。波動は『非局所的』で、空間と時間を超えて拡がり、その瞬時的な作用は至るところに及ぶ。波動は同時にあらゆる方向に拡がり、他の波動と重合し一体となり、新たな実在(創発的な全体)を形成する(Zohar and Marshall 1994: 326)。本書では、「創発的な全体」を生み出しているように見える様なグローバルな「波動」をいくらか類推的に分析することを試みる。とはいえ他方では、「空間的、時間的に定位され計測可能」である無数の単体粒子、つまり人間と社会集団が確固として存在している。」(p.215)
このように、この本では、アーリは関連する文献を数多く引用・参照しているが、あまり自身の独自の考え方や具体的な分析事例は書かれていない。そのため、この本は、アーリの主張・研究として読むというよりは、関連文献への索引として読むほうがいいかもしれない。そう考えれば、非常に広範な文献をカバーしているので便利だ。
ただし、アーリはルーマンの理論に批判的な指摘をしているが、僕からするとその指摘は適切でないように思う。むしろ、アーリの議論は、ルーマンの社会システム理論で補強するとよいのではないかと思える。そういう意味で、この本を読むときには、アーリの評価をすべて鵜呑みにせず、実際にその文献を読んで、自分で関係付けをし直す、というのがよいだろう。
この本の最後に、次のような記述がある。超領域的な研究を志向する僕らを勇気づけるので、少し長くなるが引用したい。
「ドガンとパールは、社会科学の革新における「知の移動」の重要性を示している(Dogan and Pahre 1990)。彼らは二十世紀の社会科学についての広範な調査に基づきながら、革新は基本的に、学問分野の内部に凝り固まった学者からも、あるいはかなり一般的な「学際的研究」をおこなう学者からも生まれないということを明らかにしている。むしろ革新は、学問分野の境界を横断する学問的移動、つまり彼らが「創造的な境界性(マージナリティ)」と称するものを生み出すような移動によってもたらされる。社会科学において新しく生産的なハイブリッド性を生み出すのに役立つのがまさにこの境界性であり、それは、学問分野の中心から周縁へと移動し、その境界を横断していくような学者によってもたらされる。こうしたハイブリッド性は、制度化された下位分野(たとえば、医療社会学)や、よりインフォーマルなネットワーク(たとえば、歴史社会学)を構成することができる(Dogan and Pahre 1990: chap.21を参照)。この創造的な境界性は、複合的で、重層的で、離接的な移動過程、つまり学問分野/地理/社会の境界を横断して生じうる過程に起因する。知の移動は社会科学に適しているように思われる。」(p.368)
この部分から僕は、分野にこだわらず自らの研究をすすめた結果、渡り歩いた領域が、創造的な境界性を生むのだ、というふうに理解した。システム理論、モデリング・シミュレーション技法、コラボレーション技法、パターン・ランゲージ、ネットワーク分析、経済物理学、量子力学などなど、これらは分野としてはかなりバラバラなものであるが、僕の中ではつながっている。もちろん、なんでもつながるわけではないから、内と外を分ける、境界線はある。それこそが、「創造的な境界性」の意味するところではないだろうか。DoganとPahreの文献を実際に読んで、さらに考えてみたい。
最近読んだ本・面白そうな本 | - | -
 井庭研 2008年度春学期 研究発表会
井庭研 2008年度春学期 研究発表会


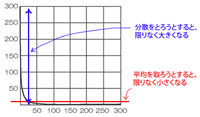


 大学院プロジェクト「インターリアリティ」プロジェクトが始まった。
大学院プロジェクト「インターリアリティ」プロジェクトが始まった。





 天気がよかったので、今日のゼミは鴨池のほとりでやることにした。せっかくの晴天なのに教室にいると気分が滅入るかな、と思って。外が明るい分、部屋の中はどうしても影になってしまうから。
天気がよかったので、今日のゼミは鴨池のほとりでやることにした。せっかくの晴天なのに教室にいると気分が滅入るかな、と思って。外が明るい分、部屋の中はどうしても影になってしまうから。 自生的秩序の研究、生命・複雑系のアートなど、僕からみると、どの研究もとても面白そうなものばかり。今後の進展が楽しみだ。
自生的秩序の研究、生命・複雑系のアートなど、僕からみると、どの研究もとても面白そうなものばかり。今後の進展が楽しみだ。 1年ほど前は、みんな頼りなくて「最高学年として大丈夫かなぁ?」と心配したもの。でも、不思議なもので、だんだん最高学年としての自覚がでてきて「腹をくくる」ことができた後は、ますます活躍して輝き、信頼のおける仕事・研究をこなすようになる。今回の卒業生たちも、そのようにして井庭研で花を咲かせてきた。
1年ほど前は、みんな頼りなくて「最高学年として大丈夫かなぁ?」と心配したもの。でも、不思議なもので、だんだん最高学年としての自覚がでてきて「腹をくくる」ことができた後は、ますます活躍して輝き、信頼のおける仕事・研究をこなすようになる。今回の卒業生たちも、そのようにして井庭研で花を咲かせてきた。
 テイクオフラリーというのは、「SFCから飛び立つ(テイクオフする)人たちの集まり(ラリー)」という意味の、SFC独自の卒業パーティーだ。1期生が卒業したときから続いている伝統的なイベントで、僕も学部を卒業した時には実行委員として映像を制作したりした。当時はSFCで開催されていたが、ある時期から船上で行われるようになったのだが、今年は久しぶりに船から陸に戻っての開催となった。会場は、横浜みなとみらいの「アートグレイス・ポートサイドヴィラ」。よく結婚式で使われる会場で、雰囲気のいいところだ。パーティーの最後には、慶應の応援歌である「若き血」を、みんなで肩を組んで何度を歌った。
テイクオフラリーというのは、「SFCから飛び立つ(テイクオフする)人たちの集まり(ラリー)」という意味の、SFC独自の卒業パーティーだ。1期生が卒業したときから続いている伝統的なイベントで、僕も学部を卒業した時には実行委員として映像を制作したりした。当時はSFCで開催されていたが、ある時期から船上で行われるようになったのだが、今年は久しぶりに船から陸に戻っての開催となった。会場は、横浜みなとみらいの「アートグレイス・ポートサイドヴィラ」。よく結婚式で使われる会場で、雰囲気のいいところだ。パーティーの最後には、慶應の応援歌である「若き血」を、みんなで肩を組んで何度を歌った。
 卒業式や修了式(修士の卒業式)は、日吉記念館で行われた。華やかな袴姿の人たちも多く、みんな晴れやかな笑顔をしていて、とても素敵な空間になる。卒業式の日はあいにくの雨模様だったが、会場はとても晴れやかな空気で詰まっていた。僕は一眼レフのカメラを片手に、井庭研卒業生たちの写真を撮る。パシャ。パシャ。そしてみんなで一緒に撮ってもらう。こんなふうにして、卒業式後の時間は素敵な記念の時間に変わっていく。(この日吉記念館は近々建て替えられるらしい。とてもシックで「深い」感じのする建物だけに残念だ。卒業式の重みは、この建物からもきていると思う。)
卒業式や修了式(修士の卒業式)は、日吉記念館で行われた。華やかな袴姿の人たちも多く、みんな晴れやかな笑顔をしていて、とても素敵な空間になる。卒業式の日はあいにくの雨模様だったが、会場はとても晴れやかな空気で詰まっていた。僕は一眼レフのカメラを片手に、井庭研卒業生たちの写真を撮る。パシャ。パシャ。そしてみんなで一緒に撮ってもらう。こんなふうにして、卒業式後の時間は素敵な記念の時間に変わっていく。(この日吉記念館は近々建て替えられるらしい。とてもシックで「深い」感じのする建物だけに残念だ。卒業式の重みは、この建物からもきていると思う。) 大学の教員をやっていると、毎年春は複雑な気持ちになる。研究会を通じて大きく成長し、「ようやく一緒に研究や仕事ができるようになった」と思った瞬間、卒業してしまうからだ。僕が教え、学生が教わるという単純な関係性ではなく、まさに「半学半教」のかたちで一緒に考え試行錯誤をともにした「仲間」なのだ。「ようやくここからが面白いところなのに」と思いながら、毎年卒業生を見送る。その反面、卒業生たちが社会のいろいろなところで活躍すると思うと、それはそれでうれしい。
大学の教員をやっていると、毎年春は複雑な気持ちになる。研究会を通じて大きく成長し、「ようやく一緒に研究や仕事ができるようになった」と思った瞬間、卒業してしまうからだ。僕が教え、学生が教わるという単純な関係性ではなく、まさに「半学半教」のかたちで一緒に考え試行錯誤をともにした「仲間」なのだ。「ようやくここからが面白いところなのに」と思いながら、毎年卒業生を見送る。その反面、卒業生たちが社会のいろいろなところで活躍すると思うと、それはそれでうれしい。