『決断力』(羽生善治)に羽生さんの創造性を見る
将棋棋士の羽生善治さんの『決断力』 を読んだ。
を読んだ。
非常に示唆に富んだ本で、大変興味深く読ませてもらった。
羽生さんがどういう人なのかがわかるとともに、将棋の世界がどういうものなのかも垣間見ることができた。そして、将棋を指すということについて、僕は何もわかっていなかったと思わざるを得なかった。将棋は無限の世界であるという羽生さんが、その世界にいかに向き合っているのか。その世界観が大変興味深い。また、コンピュータの登場が将棋の世界をどのように変えているのかについても面白かった。
しかしながら、より興味深いのは、将棋を通じて育まれた彼の考え方が、将棋の世界のみならず、多くの物事に通じる普遍性をもっているということだ。まさに、個を突き詰めたゆえの普遍性だ。彼は将棋とスポーツには共通点があると語り、またビジネスや研究にも通ずるものがあるという。僕は、この羽生さんが語る「エクスパティーズ」(熟練)の本質に、ただただ頷くばかりであった。
その普遍性を羽生さんも十分承知していて、それぞれの話題の後に必ず「将棋にかぎらず…」として、読者の携わる世界でも同様であることに言及している。このことが、本書が将棋好き以外の読者にも広く読まれてきた理由なのだろう。
この部分で、将棋における「創造性」についてのイメージがぐっと広がった。
これまで、僕のなかには、将棋は有限の配置の組合せのなかでの勝負だというイメージがあったが、その見方は将棋の本質を矮小化した見方であるということがわかった。その有限性はたしかに「神」の視点からは正しいかもしれないが、人間は神の位置にいるわけではない。あくまでも広大に広がる展開の一節点に立っているにすぎない。
将棋が有限の局面の集合でしかないという見方は、まるで小説や詩が有限の文字の組合せに過ぎないと看做すようなものなのである。それでは、創造性という存在は無化されてしまう。もし小説や詩に創造性を見いだすならば、将棋にも創造性を見いだすことができるはずだ。僕はこの立場をとっているし、とりたいと思う。
羽生さんのこの本には、そういった将棋の創造性についての彼の考え方が書かれているように、僕には思えた。これは僕の過剰な読み込みかもしれない。しかし、僕にとっては、この本はその点において、大変示唆に富む本であったことは間違いない。
● 『決断力』 (羽生善治, 角川oneテーマ21, 角川書店, 2005)
(羽生善治, 角川oneテーマ21, 角川書店, 2005)
非常に示唆に富んだ本で、大変興味深く読ませてもらった。
羽生さんがどういう人なのかがわかるとともに、将棋の世界がどういうものなのかも垣間見ることができた。そして、将棋を指すということについて、僕は何もわかっていなかったと思わざるを得なかった。将棋は無限の世界であるという羽生さんが、その世界にいかに向き合っているのか。その世界観が大変興味深い。また、コンピュータの登場が将棋の世界をどのように変えているのかについても面白かった。
しかしながら、より興味深いのは、将棋を通じて育まれた彼の考え方が、将棋の世界のみならず、多くの物事に通じる普遍性をもっているということだ。まさに、個を突き詰めたゆえの普遍性だ。彼は将棋とスポーツには共通点があると語り、またビジネスや研究にも通ずるものがあるという。僕は、この羽生さんが語る「エクスパティーズ」(熟練)の本質に、ただただ頷くばかりであった。
その普遍性を羽生さんも十分承知していて、それぞれの話題の後に必ず「将棋にかぎらず…」として、読者の携わる世界でも同様であることに言及している。このことが、本書が将棋好き以外の読者にも広く読まれてきた理由なのだろう。
「棋士は指し手に自分を表現する。音楽家が音を通じ、画家が線や色彩によって自己を表現するのと同じだ。小説家が文章を書くのにも似ている。二十枚の駒を自分の手足のように使い、自分のイメージする理想の将棋を創りあげていく。ただ、将棋は二人で指すものなので、相手との駆け引きのなかで自分を表現していく。その意味では、相手は敵であると同時に作品の共同制作者であり、自分の個性を引き出してくれる人ともいえる。」(p.67)
この部分で、将棋における「創造性」についてのイメージがぐっと広がった。
これまで、僕のなかには、将棋は有限の配置の組合せのなかでの勝負だというイメージがあったが、その見方は将棋の本質を矮小化した見方であるということがわかった。その有限性はたしかに「神」の視点からは正しいかもしれないが、人間は神の位置にいるわけではない。あくまでも広大に広がる展開の一節点に立っているにすぎない。
将棋が有限の局面の集合でしかないという見方は、まるで小説や詩が有限の文字の組合せに過ぎないと看做すようなものなのである。それでは、創造性という存在は無化されてしまう。もし小説や詩に創造性を見いだすならば、将棋にも創造性を見いだすことができるはずだ。僕はこの立場をとっているし、とりたいと思う。
羽生さんのこの本には、そういった将棋の創造性についての彼の考え方が書かれているように、僕には思えた。これは僕の過剰な読み込みかもしれない。しかし、僕にとっては、この本はその点において、大変示唆に富む本であったことは間違いない。
● 『決断力』
最近読んだ本・面白そうな本 | - | -
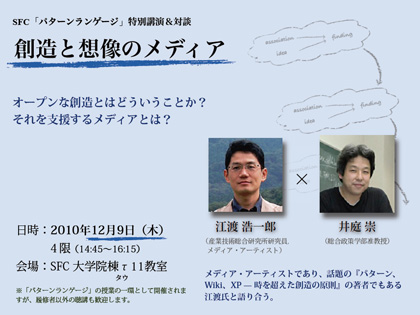
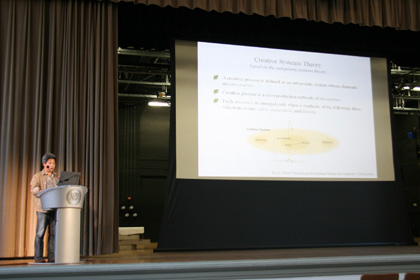
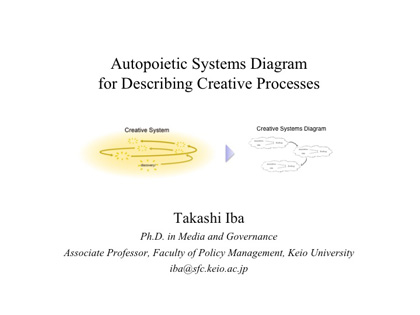
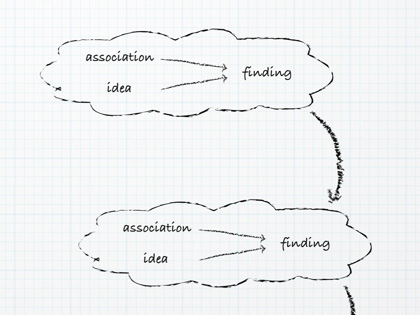
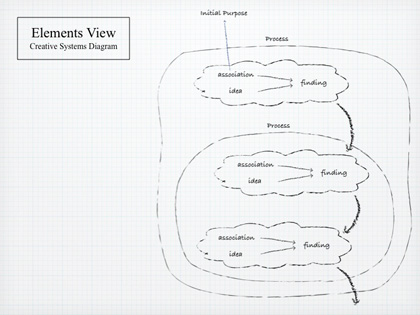
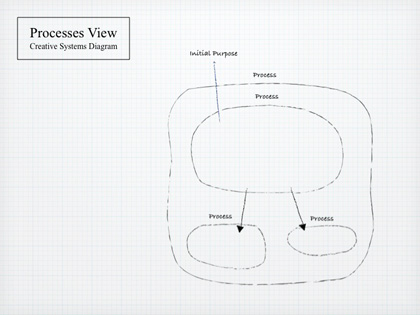
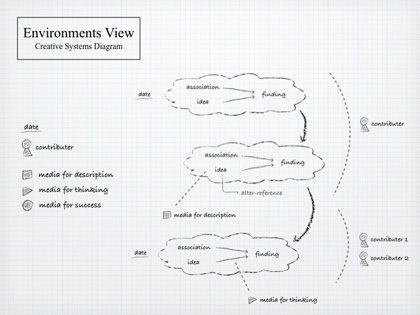
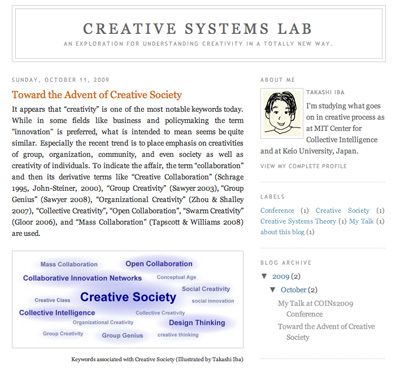


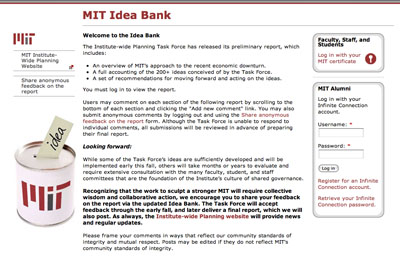

 夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです!
夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです! ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。
ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。
 僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。
僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。 さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。
さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。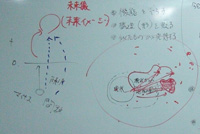 このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。
このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。

